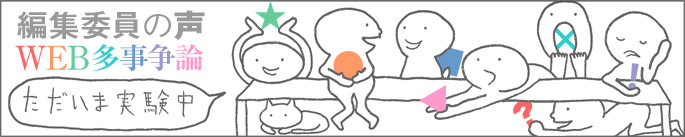No.131に関するツリー
- ▼-筑紫哲也の書斎 [WEB多事争論編集委員 吉岡弘行] (05/15 13:35)
- ├Re:筑紫哲也の書斎 [神戸とみ子] (01/07 18:24)
[131] 筑紫哲也の書斎
- 投稿者
- WEB多事争論編集委員 吉岡弘行
- 投稿日
- 05/15 13:35
先日、赤坂の筑紫さんの書斎を久しぶりに訪れた。
この部屋には生前、何度か訪れていたのだが、大きな机には常に自ら切り抜いたとみられる新聞のスクラップやディレクターから手渡された資料が常に山積みになっていた。
スクラップなどネット時代に古臭いと思われるかもしれない。作家の佐藤優氏は『国家の陰謀』(小学館 2006年)の中で、新聞の切り抜きという営みの重要性を次のように説いている。
「インターネットの普及に伴い、新聞のスクラップに割く時間を無駄と考え、データベースに頼る傾向が強まっているが、私の知る一級の情報専門家は“例外なく”自らの手で切り抜きを行っている」
部屋の壁の一面には、天井まで達する大きな書棚が配してあって、膨大な蔵書が収められていた。
筑紫さんは時に大雑把な性格だと誤解されやすいところがあったが、素顔はとても几帳面な人で書棚にもそれはあらわれていた。少し大きめの黄色いポストイットに自筆で「特別な本」「憲法関係」「沖縄」「メディア関連」と書かれた付箋が張り付けてあり、テーマごとにきちんと本が整理されていた。
この書斎に前回、足を踏み入れたのは筑紫さんが去年11月7日に亡くなって3日後のことだった。
追悼特番を制作することになり、次女のゆうなさんに書斎を案内してもらい、キャビネットの中から『残日録』が見つかったのだ。番組は急きょ内容を大幅に変更してこの『残日録』を中心に構成しなおした。
今回、書斎を訪れたのは筑紫さんの蔵書を、教鞭をとった母校の早稲田大学に『筑紫文庫』として寄贈することになったからだ。そして、ゆうなさんからどうしても手元に残しておきたい本を私に選んでほしいと頼まれたのだ。「長らく父と仕事をした吉岡さんなら父が愛着を持っていた本を選んでくれるのでは」という理由からだった。
本の整理は午前中からゆうなさんがとりかかった。
筑紫さんの自著や師と仰いだ丸山真男氏の著作、番組にたびたび出演していただいた立花隆氏、藤原帰一氏、寺島実郎氏らの著作などをゆうなさんが大まかに選んでいた。
私は夜から作業に加わり、一冊ずつ説明をしながら、およそ20冊の本を追加して残しておくよう提案した。
政治家の著作では後藤田正晴さんの『情と理』。
オーラルヒストリーの第一人者・御厨貴さんが聞き取りをした“カミソリ後藤田の回顧録”である。後藤田さんは警察官僚のトップから政治家になったが、特に晩年は憲法の枠を逸脱した自衛隊の海外派遣や精緻さを欠く憲法論議に苦言を呈していた。筑紫さんが最後まで尊敬していた政治家だった。『情と理』はTBSのキャスタールームにも置いてあって、ことあるごとに読み返していたようだ。上・下に分かれた2冊の本には多数の付箋が付いている。
小説家では瀬戸内寂聴さんの『場所』。
この本も筑紫さんにとっては特別の愛着があったようだ。「ニュース23」では以前、キャスターが輪番でお薦めの本を紹介する『コレヨモ』というコーナーがあった。筑紫さんはこの寂聴さんの『場所』の一節を朗読して紹介したのだが、その時の拡大コピーが本の中にまだ挟まれていた。
中沢新一さんの『アースダイバー』という本も残すことにした。
この本は私もたまたま気になって読んでいて、筑紫さんと内容について「面白い」と意見が一致した本だ。縄文時代の東京の地図が付録についていて、現代の東京の成り立ちを独自の視点から解き明かしたユニークな本である。
そのほかにチョイスしたのは、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』、キャロル・グラックと姜尚中氏らの共著『日本はどこへいくのか』、ロバート・B・スティットの『真珠湾の真実』、アル・ゴアの『不都合な真実』など・・・・。20冊の中には筑紫さんから「読んでおいたほうがいいよ」と言われ、結果的に私の書棚にもある本が何冊か含まれることになった。
一通り整理を終えてゆうなさんと並んでしばらく思い出話をした。
視線の先にあったのは、最後の放送になった多事争論「変わらぬもの」という筑紫さんの直筆だった。
[165] Re:筑紫哲也の書斎
- 投稿者
- 神戸とみ子
- 投稿日
- 01/07 18:24
スロ-ネットに関わってから始まった「地域を知る学び」スロ-ライフ運動は、私の今まで生きてきた集大成のように、子や孫に伝えていきたい日本の伝統文化です。今の世直しです。子育て教育に必要な現実を知る経験を孫と共に、旅と遊びで学んで欲しい。「私の抱負2011」の夢です。ふるさと再生仕掛人として地域発信を続けて活きたいと思っています。
読んで涙が出る思いです。
筑紫さんとゆっくり語ってみたかったと・・・
「地域を知る学び」筑紫さんの意を継いで、スロ-ライフ運動をしている者として、大事にしてきた「平和への思い」が伝わってきます。
私が住んでいる群馬県南牧村は少子高齢化が進み、高齢化率日本1位と言われながらも、元気なお年寄りが美味しい野菜を作って、近隣が助け合って生きています。ですが、都会一極集中による就職難や人口流出は免れず、孤独死や自殺など起きてはならない現実は目を背けられずです。日本の縮図と言っても過言ではありません。
そんな今まで関わったスロ-ライフ関係の書籍や筑紫さんが書いた本などを「スロ-ライフ文庫」として、この南牧村に寄贈され今預かり状態です。地方分権の世の中に向けて、地方再生への起爆剤になればと期待したいと思いで読んで居て勝手に嬉しくなり読み取れました。
早稲田大学に一部「筑紫文庫」が出来るという話、なんだか筑紫さんの「意」が歩き出したように感じます。
筑紫哲也氏の書斎を見てみたくなりました。
http://ameblo.jp/hurusatosaiseisikakenin/entry-10704512666.html