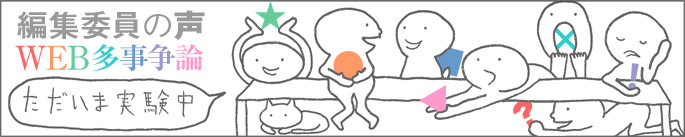No.132に関するツリー
- ▼-「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」 [WEB多事争論編集委員 天野環] (09/26 10:00)
- ├Re:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」 [medito] (10/02 16:07)
- │├meditoさんへ [Web多事争論編集委員吉岡弘行] (10/19 14:42)
- ││├Re:meditoさんへ [medito] (10/28 00:20)
- │││├Re[2]:meditoさんへ [ms] (11/18 19:52)
- ││││└msさんへ [medito] (11/24 09:11)
- │├Re[2]:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」 [ms] (10/20 10:27)
- ││├meditoさんへ [ms] (11/26 12:32)
- │││├msさん [medito] (11/26 19:15)
- ││││├medito さんへ [ms] (11/27 12:10)
- │││││├msさんへ [medito] (11/27 14:12)
- ││││││└meditoさんへ [ms] (11/28 01:25)
- ││││││ ├msさん [medito] (11/28 17:12)
- ├Re:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」 [木村] (12/16 20:41)
[132] 「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」
- 投稿者
- WEB多事争論編集委員 天野環
- 投稿日
- 09/26 10:00
早いもので自民党の歴史的惨敗・民主党圧勝から一ヶ月が経とうとしています。マスメディア各社の「世論調査」なるものによる、新内閣の「支持率」も、あの小泉内閣に次ぐ高支持率を記録しました。鳩山首相・オバマ大統領の初の首脳会談では、新聞・テレビの「見出し」が、ほぼ全社「予定稿」通り「緊密な同盟関係を確認」で並んでいます。政権は変わったものの、読者・視聴者の目にする「見出し」は相も変わらず矛盾だらけの「官僚用語」のオンパレードです(端的に何故「軍事同盟」と言い切れないのでしょうか)。新総理が風に乗った「伝書鳩」にすぎないのかどうか睨みつつ、マスメディアはまず自ら「政治のことば」を変えるべきではないかと、戒めを込めて痛切に感じました。政権交代を機に、「変わるもの」と「変わらないもの」を巡り、この一月を少しだけ振り返ります。
「悼」。一文字だけ彫られた小さな石碑の除幕式が、東京・荒川土手の脇、民家の隣で営まれました。86年前、関東大震災(1923年9月1日)時の流言蜚語で、6000人以上の朝鮮人が虐殺され(そして中国人・さらに日本人も・・・)、この旧四ツ木橋付近もその中心地の一つとされています。震災時の朝鮮人虐殺を巡る追悼式は例年、9月最初の週末に毎年変わることなく続けられています。「自警団」らによって殺された名も無き人々を悼む碑が、地元有志の手により今年ようやく建立されました。虐殺時には鉄棒で殴られたり、竹やりで刺されたりと、その証言は様々ですが、当時を知る人も今は殆どいません。8月29日、残暑厳しい土曜の午後でした。10数名によるささやかな会を後に、私はその足で池袋に向かいました。麻生・鳩山両氏が「最後のお願い」を訴える繁華街に。
池袋駅東口を埋め尽くしていたのは、多くが「日の丸」の小旗を振りかざした群集でした。麻生陣営の演説です。人の波をなんとか掻き分けて、地下道を抜けて西口に回ると、若干、若者の割合が目立ちます。鳩山陣営です。しかしマスメディアを含め、何という人の数でしょう。「閉塞感」漂う中、ようやく行われる総選挙。世論の関心が高いのは分ります。期日前投票が過去最高だったことも頷けます。しかしながらこの圧倒的な人波と熱狂ぶり、そのどこに向かうか判らない矛先には、(「政権交代への期待感」ではなく)恐怖感すら覚えざるを得ませんでした。この時点で既に、メディア各社の「情勢分析最終予測」は「民主党席獲得議席300」を超えています。そして翌30日、「予定稿」通り、政権は「変わり」ました。
今回の選挙結果を、自民党政治の崩壊と共に、「方向性」さえ決まれば「思考停止」のまま雪崩打つニッポン人の「国民性」などと片付けるのは容易い話です。しかしながら私は、この歴史的総選挙の前日、同じ日の異なる二つの「風景」、「少人数の除幕式」と「圧倒的多数の集会」を忘れないでおこうと思います。86年前に多数の日本人によって殺された中国・朝鮮人を悼む人々の姿と、今年池袋で写メールを撮り続けた人々の姿。同じ「普通」のニッポン人の姿を。
来年は、日韓「併合」から100年、そして日米安保条約「改定」から50年を迎える節目の年です。鳩山政権は「東アジア共同体」や「対等な日米関係」を謳いますが、鳩山氏個人は「自衛軍」の保持を目指す改憲論者であるのは周知の事実です。「自衛軍」の保持は、自主憲法制定を党是とする自民党の憲法草案と全く同じ表現です。そしていよいよ来年から、国会での憲法改正の発議が「解禁」されます。私は、天皇制は即刻廃止すべきだと考えますので、その意味では「改憲」サイドですが、「前文」と「九条」に関しては手を付ける必要はないと考えます。政権は「変わり」ましたが、それ以前に「変えてはならぬもの」が改めて浮き彫りになってきたようにも思います。幸か不幸か、現在改憲問題は蚊帳の外ですが、そもそも今の選挙制度による今回のような民主党か自民党かといった、二大政党制が果たしてニッポン人を幸福にするのかどうかを含めて、です。私自身は、1993年の細川政権末期から94年の羽田・村山政権と、三代に亘って旧首相官邸で「総理番記者(良くも悪くも「犬」です)」をしておりました。あれから16年、時代(とき)の勢い(無責任な表現ですね)で「変わるもの(「失政としての小選挙区制導入」)」はあっても「変えてはならぬもの(日本国憲法)」は確実に存在すると思っています。そして「変わってしまったもの」も、再び「変えなくてはならぬ」であろうと、「犬」の眼で考えています。(了)
[133] Re:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 10/02 16:07
いろいろな立場がありますよね。
私は憲法九条は即刻変えるべきだと思いますし、一条に手を着ける必要はないとも思う。
「変えるべきもの」と「変えるべきじゃないもの」、ですね。
[139] meditoさんへ
- 投稿者
- Web多事争論編集委員吉岡弘行
- 投稿日
- 10/19 14:42
なぜ戦争の放棄を定めた九条を「即刻変えるべき」と思ってらっしゃるのか、具体的な理由が聞きたいたいところです。
私は、核兵器根絶に向けて世界が一丸になろうとしているときに、憲法の前文と九条は、以前にもまして輝きを増していると考えています。
憲法改正をいう人は、本当に憲法を“読んでいる”のか疑問です。
このことは筑紫さんが新著『若き友人たちへ』(集英社新書・10月発売)でも触れられていますので、お読みになられると参考になろうかと思います。
[142] Re:meditoさんへ
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 10/28 00:20
なぜ変えるべきかって、そりゃ現状と乖離しているからに他なりませんよ。それ以外に何の理由があるんですか?
あなたは憲法九条を変えるべきではないと思ってる。そりゃ結構ですが、現に日本には自衛隊という、立派な戦力があるじゃないですか。
それともあの政府のふざけた解釈改憲をそのまま認めるつもりですか。
護憲を唱える方達は、どうして憲法の字面だけにこだわって、その実は全く機能していないという現状にてんで無頓着なんですかね。
むしろ、本当に憲法を読んでいるのかという疑問はそちらのほうにお返ししたい。
条文と実態の間に著しい乖離がある。これは立憲政治の危機でしょう。
本当に憲法のことを真剣に考えているならば、速やかに条文を改善するために動くべきであって。
言うならば、護憲運動は憲法を殺して条文を生かせようとしている。肝心の条文が空文化して、憲法の実効性が失われていても関心が無いわけです。
それはおかしいでしょう。
[146] Re[2]:meditoさんへ
- 投稿者
- ms
- 投稿日
- 11/18 19:52
現状と乖離しているから改正するという意見には同意しかねます。
確かに、憲法と現実が乖離しているのは事実です。
しかし、現実というのは人為的なものでもあり、予測不可能なものでもあります。
改正したとしても、新しい現実がでてきたら、どう対応するのでしょうか。
新たな現実が生まれる可能性は否定できません。
その時、再び解釈改憲を既成事実化して、新しい現実にすり寄るのでしょうか。
現実を憲法に近づけるという考え方もあります。
大事なのは、「どういう国にしたいのか」という戦略を持つことではないかと思います。
そうした戦略がなければ、改正しても危ういのではないかと思います。
憲法とは、一般的に国の理念や目標を定めたものです。
それに向けて一歩でも近づこうとするものでなければならないと私は思います。
[149] msさんへ
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 11/24 09:11
>現状と乖離しているから改正するという意見には同意しかねます。
同意しかねるもなにも、それでは憲法の意味がまるで無いということなのですが、いかかですか。
憲法は国民による統治機関に対する「鎖」、統治機関による国民に対する「約束」ですよ。
鎖が鎖として機能せず、約束が約束として果たされていないことが問題なんです。憲法が現状と乖離しているのではたまったものではありません。
>改正したとしても、新しい現実がでてきたら、どう対応するのでしょうか。
>新たな現実が生まれる可能性は否定できません。
>その時、再び解釈改憲を既成事実化して、新しい現実にすり寄るのでしょうか。
その時は憲法をまた改正するだけですよ。
解釈改憲なんてする必要はありません。
>憲法とは、一般的に国の理念や目標を定めたものです。
>それに向けて一歩でも近づこうとするものでなければならないと私は思います。
憲法が国の理念や目標を定めたものだとあなたがお思いになるのは自由ですし、全く構わないのですが
憲法とは一般的に「国民による統治機関への命令」であり、「政府に恣意的な権力行使をさせないための法律」のことをいうのです。
もちろん理念や目標であるという一面もありますが、然るに憲法の最も重要な機能はそれではないのですよ。
わかりますでしょうか。日本国憲法に照らせば、どう考えたって自衛隊という暴力装置の存在は違憲ですよ。それなのに、「解釈改憲」という統治機関の恣意的な政治判断がまかり通っている。
「戦略が無ければ改正しても危うい」と仰られましたが、一体どちらが危ういかといえば、私は憲法が統治機関に対する鎖として機能していない現状のほうが危ういと思うし、恐怖ですね。
憲法を改正して自衛隊を認めるというのは、現実に擦り寄るわけでもないし、戦略もなしに場当たり的に改正する、ということではないんですよ。
憲法に自衛隊を明記させ、然るべき地位を与えること。これは、日本国憲法に実効性を取り戻す、ということです。
考えても見てくださいよ。明日にでも解釈改憲でどうにでもなってしまうような暴力機関。恐ろしいでしょう。
それを憲法を改正しきちんと定義することで、国民が制御できるようにしようと。
そういうことです。
[141] Re[2]:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」
- 投稿者
- ms
- 投稿日
- 10/20 10:27
meditoさん、吉岡さんへ
筑紫さんが「我々は憲法を使いこなしているのか」と問題提起されていたのを思い出します。
近著でも指摘されていました。それは説得力のある話だと思います。
憲法は前文から第103条までで成り立っていますが、それは決して覚えられない量ではありません。
しかし、我々は憲法に関して知らないことが実に多い。
ある事件や出来事と絡めて、憲法の条文が頭に浮かぶことがなければ、自分の権利を主張することもありません。
近頃の社会の出来事や風潮からもわかるように、公共の福祉なんて概念は、どこか遠くに飛んで行ってしまったかのようです。それだけ、蔑ろに扱ってきた面があることは確かだと思います。
まずはボロボロになるまで使いこなして、自分のものにすることから始めるべきではないでしょうか。
[151] meditoさんへ
- 投稿者
- ms
- 投稿日
- 11/26 12:32
憲法が「国民による統治機関への命令であり、政府に恣意的な権力行使をさせないための法律」だからこそ問題があるのだと思います。
毎回、憲法論議を主導しているのは、統治機関の側ではないでしょうか。積極的に問題提起するのもそうです。
国民よりも統治機関が変えたがっているように見えます。
政府が恣意的な判断をしているのであれば、なおさら順守させる方向に向かわせるのが本来のあり方だと私は思います。
政府にとって使い勝手が悪くなったために、改正しようとする。また、都合が悪くなったら改正する。
これを国民が制御している状態と言えるでしょうか。
鎖が機能していないということですが、この国には集団的自衛権が認められていません。ぎりぎりの段階で拒否しているのが9条だと思います。
憲法には、9条以外にも約束が果たさせていない問題はあります。
「一人ひとりの生存権の面倒は見ていられないから改正しよう」「男女間には未だに社会的な格差があるから改正しよう」という人はいません。
これらも現状から乖離していると思いますが、いかがでしょうか。
[152] msさん
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 11/26 19:15
:>毎回、憲法論議を主導しているのは、統治機関の側ではないでしょうか。積極的に問題提起するのもそうです。
>国民よりも統治機関が変えたがっているように見えます。
おそらくは保守派の、憲法改正派の国会議員のことを指してそう仰っているのでしょうが、彼らは国民の代弁者なのですが何か問題あるのでしょうか。
内閣、国会、まあ統治機関といえばこれらですけど、その構成員はそのほぼすべてが国民に間接的もしくは直接的に選ばれた者たちです。
逆に伺いたいのですが、彼らが問題提起しなければ誰がするのですか。
>政府が恣意的な判断をしているのであれば、なおさら順守させる方向に向かわせるのが本来のあり方だと私は思います。
では、戦力の不保持を明記しておきながら自衛隊があるという矛盾を、条文の改正なし解釈改憲なし、という条件で一体どのように解決すればいいのかを教えてください。
>政府にとって使い勝手が悪くなったために、改正しようとする。また、都合が悪くなったら改正する。
>これを国民が制御している状態と言えるでしょうか。
お言葉ですがmsさん、これは感心できない論法です。
確かにあなたの仰ってるとおりであるならば、それは制御している状態であるとは言い難い。しかしだからといって、憲法改正議論がすべてそうだとは限らないでしょうし、憲法9条の改正議論がそうだというのはmsさん個人の主観かレッテルにすぎないわけじゃないですか。
そのようなことを言いだしてしまえば、一切の改正議論ができなくなります。
>鎖が機能していないということですが、この国には集団的自衛権が認められていません。ぎりぎりの段階で拒否しているのが9条だと思います。
明日にでも解釈が変われば認められてしまうわけですが、「ぎりぎりの段階で拒否してるのが9条」とは、何とも頼りにならない鎖です。
>憲法には、9条以外にも約束が果たさせていない問題はあります。
>「一人ひとりの生存権の面倒は見ていられないから改正しよう」「男女間には未だに社会的な格差があるから改正しよう」という人はいません。
当たり前じゃないですか。
>これらも現状から乖離していると思いますが、いかがでしょうか。
文脈からして、どうも「生存権の保障も男女平等も実現されてないじゃないか。これらが実現されるべき目標であると同じように、9条だって実現されるべき目標なんだ」という論理のようですが
憲法において「実現されるべき目標」というのは、たとえば生存権のような特定の権利条項においてのみ言えることです。
これらは現状から乖離しているから、条文に少しでも近づけるように努力すればいい。然るに憲法9条はそういった「努力目標」の類ではありませんので。
[153] medito さんへ
- 投稿者
- ms
- 投稿日
- 11/27 12:10
国民の代弁者が国会議員であるのはもちろんです。
しかし選挙の際、彼らは憲法改正を争点に掲げているでしょうか。選挙になると妙に歯切れがよくないところがあります。
憲法改正を全面に出してきた首相も何人かいましたが、突発的で後が続かない。個人的な思い入れだけでは困ります。
そして国民投票法が成立しても憲法調査会は開かれません。
国の骨格である憲法に対して、あまりに対応が軽いと思いませんか。
一時の乗りで押し切ろうとしていたのではないかと思わせます。
問題提起という言い方には語弊があったかもしれません。
改正するにも、時間をかけて国民に問い続けるべきです。
国民の側から「こういう憲法にしたい」という積極的な意見がでるような土壌を作ることもなく、統治機関の中だけで事を進めて改正しても意味がないと思います。
そういう意味で、「国民よりも統治機関が変えたがっているように見える」「国民が制御することになるのか」と申しました。
自衛隊は確かに戦力と言えますが、それは狭義においてです。広義の意味では戦力とは言えません。
なぜなら、国の基本原則・制度等において戦争遂行能力を持たないからです。
半分はまだ9条の力が効いています。
改正したからといって、諸問題が劇的に解決することはありません。
戦争違法の時代であり、核軍縮の流れも動き出そうとしています。
何十年、もしくは百年単位になるかもしれませんが、長期的な視点から、現実を9条に近づけるよう努力することが有益ではないかと私は思います。
[154] msさんへ
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 11/27 14:12
>憲法改正を全面に出してきた首相も何人かいましたが、突発的で後が続かない。個人的な思い入れだけでは困ります。
そんなに心配しなくても国民投票があるし、あれだけハードルの高い改正手続きの連続ですから「個人的な思い入れ」だけで改正することなんか出来やしません。
>そして国民投票法が成立しても憲法調査会は開かれません。
>国の骨格である憲法に対して、あまりに対応が軽いと思いませんか。
思いませんけど、と言ってしまえばおしまいですが...。
あえてコメントさせていただくならば、あまりに憲法にたいして対応が軽いのは護憲派のほうですよ。国の骨格が機能していないことに無頓着すぎ。
>改正するにも、時間をかけて国民に問い続けるべきです。
>国民の側から「こういう憲法にしたい」という積極的な意見がでるような土壌を作る>こともなく、統治機関の中だけで事を進めて改正しても意味がないと思います。
こういうことを言うのは非常に心苦しいのですが、msさんのその主張の前提はほとんどが個人の主観や仮定(悪くいえば邪推)の域を出ていません。「国民に憲法改正の議論をする土壌が出来ていない」「統治機関の中だけで事を進めても意味がない」というのは、それこそ主観の極みであって、それを証明する手だてもソースもなく、したがって私が論理的に反論することも出来ないわけです。
上の「あまりに対応が軽すぎると思いませんか?」という質問もそうですが、私があなたに対して「私はそのようには思えないけど」と言えば議論が終わってしまうでしょう。そういった「そう思える」「そう見える」という非常に主観的な前提の積み重ねを続ければ、何だって肯定できるし否定も出来ます。
そこからはなにも生まれません。そのような議論を続けていれば、それこそ永遠に議論をする土壌なんて生まれないでしょう。
>自衛隊は確かに戦力と言えますが、それは狭義においてです。広義の意味では戦力とは言えません。
>なぜなら、国の基本原則・制度等において戦争遂行能力を持たないからです。
半分はまだ9条の力が効いています。
仮に何歩か譲って考えるとしても、何度も繰り返しますが、9条のような国の暴力装置について規定する条文が「半分」しか利いてないという状況が危ないんですよ。もう半分蔑ろにしてるわけで。そしてこれは、これからもう半分も蔑ろにする余地があることをそのまま意味します。半分蔑ろにしてるんだから簡単です。
>改正したからといって、諸問題が劇的に解決することはありません。
だからといって憲法改正を否定する理由にはなりませんが。
>戦争違法の時代であり、核軍縮の流れも動き出そうとしています。
>何十年、もしくは百年単位になるかもしれませんが、長期的な視点から、現実を9条に近づけるよう努力することが有益ではないかと私は思います。
では、私から提案させていただきましょう。近代の立憲主義から考えて、明らかに現状から乖離し空文化している憲法9条は異常である。改正し、憲法に実効性を取り戻すべきだ。その他新しい権利も積極的に加えよう。
その上で、9条的理念に向かって現状を理想に近づけるよう努力しましょう。これで何の問題もないのですが、いかがでしょうか。繰り返しますが、9条はそのような努力目標ではありません。きちんと機能してもらわないと困る条文です。
[155] meditoさんへ
- 投稿者
- ms
- 投稿日
- 11/28 01:25
これはあくまで私の見方なので、主観的というのは否定しません。
しかし、それを言ってしまえば「憲法の実効性が失われている」「9条は全く機能していない」という意見も、私から見ると主観的な意見なわけです。
改正したうえで、「9条的理念に向かいましょう」といっても、それに向かうことへの保証はありませんし、証明もできません。どこまで改正してそれをやろうとしているのかも見えてきません。
結局、主観と主観でぶつかりますが、それでいいのではないかと思います。
[156] msさん
- 投稿者
- medito
- 投稿日
- 11/28 17:12
憲法に「戦力の不保持」を明記しておきながら自衛隊を保持している、というのは現実にあることで、そこに矛盾があるのは火を見るより明らかでしょう。そして私はそれを指摘しているのですね。
あくまで単純な論理ですので、そこに私の主観が入りむ余地はない、ということだけを申し上げておきます。
>改正したうえで、「9条的理念に向かいましょう」といっても、それに向かうことへの保証はありませんし、証明もできません。
それはある種の禁じ手です。それを言ってしまうとなにも議論できなくなるし、行動も出来なくなります。
未来の出来事を証明したり保証したりすることができないのは当然で、それは人間の出来る芸当ではない。
そして今ここにある事実は、憲法9条とは相容れない存在が日本にある、という矛盾だけです。
もちろん主観的な意見は議論においてとても大切なものですけど、結局は客観的な事実に立脚して考えていかないといけないのです。お互いの主観の言いっぱなしでは不毛ですから。
私の意見はこんなところです。
[161] Re:「政権交代変わるものと変えてはならぬもの」
- 投稿者
- 木村
- 投稿日
- 12/16 20:41
国語の問題的に考えますと、国の名前と思われるものが4つ出てきます。
朝鮮、中国、日本、ニッポン。
関東大震災時の話題では、朝鮮、中国、日本、
現在の話題では、ニッポン
関東大震災時の話ですので、中国は、中華民国。
朝鮮に関しては、すでに大韓民国に名前を変更しています。
日本は、明治以降日本ですが、おそらく、何らかのタイミングでニッポンになったと思われていらっしゃる。
対比をされている現在と過去の情報についても、面白い。
当時を知る人も今は殆どいない、証言も多岐にわたる、確認しようがないが、変わらない事実。
現在、今まさに起こっており確認できるが、表現しない、もしくは出来ない
変わる事実。
ロマンティックでもあり、残酷でもある文章ですね。
そこで一番面白いのが、先ほど言った国の名前の中で、唯一現在の日本のものでニッポンと表現されていないものが、あります。
日本国憲法。
1923年の当時、存在しておらず、1946年に公布された、現在の憲法。
あえて、ニッポンと書かれなかった事にいろいろと考えさせてもらえます。