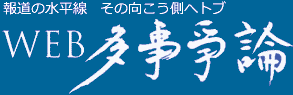No.21に関するツリー
- ▼-POST-RACIAL AMERICA???? [竹内明] (2009/3/15 0:51)
[21] POST-RACIAL AMERICA????
- 投稿者
- 竹内明
- 投稿日
- 2009/3/15 0:51
アメリカに黒人初の大統領が誕生した。就任式に臨むオバマ大統領を熱いまなざしで見つめるアフリカ系アメリカ人市民の様子は全世界に放映された。
「ポスト・レイシャル(脱人種・人種問題超越)」という言葉がメディアで盛んに使われ、オバマ大統領の誕生によって人種間の壁が取り払われることが期待されている。しかし「脱人種」とはオバマにとって最も困難な課題であろう。
2月18日付のニューヨーク・ポスト誌には、こんな漫画が掲載された。
路上に血まみれのチンパンジーが仰向けに倒れている。手前には拳銃を構えた白人警察官が二人。うち一人がこう言っている。
“They`ll have to find someone else to write the next stimulus bill.”
(次の景気対策法案を作るヤツを見つけなきゃいけないな)
コネチカット州スタンフォード米国では2月16日、体重90キロもあるペットのチンパンジーが女性に重傷を負わせ、警官に射殺されるという事件が起きていた。黒人初の大統領となったオバマをチンパンジーに例えたこの漫画に、公民権運動指導者のアル・シャープトン師らが大反発。ニューヨーク・ポスト社の前にデモ隊が押し寄せた。
年が明けてからの人種論争はこれだけではない。1月1日にはカリフォルニア州オークランドの鉄道駅で、無抵抗の黒人青年が警察官に射殺されるという事件が起きている。事件の一部始終を撮影した映像がユーチューブで公開され、市民が暴徒化する事態となった。
「公民権運動は終わったが、現実は何も変わっていない」
私は3年半前のルイジアナ州ニューオーリンズで耳にしたある男の言葉を思い出した。以下に書くのは、巨大ハリケーン「カトリーナ」に全てを奪われたある黒人男性のサバイバル体験、そしてアメリカ社会が抱える人種問題の現実である。
2005年8月29日の夕刻、アービン・ロビンスは自宅屋根裏で背中を丸め、聴覚に全神経を集中させていた。胡座をかいた彼の脚の上では、まだ生後半年の息子が寝息を立てていた。
蒸し風呂のようになった屋根裏で、何時間も過ごしたロビンス一家は疲弊しきっていた。室内には汚水の臭気が充満し、妻は熱射病の初期症状で床に倒れたままだ。
ロビンスの平屋建て住宅は、濁流に呑み込まれていた。水位は1階の天井まで達した。外の道路は深さ3㍍の水の底だ。
ハリケーン・カトリーナがルイジアナ州に上陸したのは年8月29日午前6時のことだった。カテゴリー4に勢力を落としたカトリーナはメキシコ湾岸のグランドアイルとミシシッピ川河口の間に上陸、ニューオーリンズ市にゆっくりと接近した。
信じられぬ事態が起きた。市内を縦横に流れる運河が次々と決壊し、貧しい黒人居住区であるロウアー第9地区に濁流が流れ込んだのだ。
ロビンスは、濁流が室内に流れ込んできたのは29日午前2時45分のことだったと記憶している。つまりカトリーナがニューオーリンズを直撃するよりも数時間前に堤防は決壊し始めたのだ。
トイレに行こうとベッドから抜け出たロビンスの耳に、「ゴーッ」という不気味な低音が飛び込んできた。家の外壁に物が衝突するようなドンドンという音が聞こえたかと思うと、道路と同じ高さにある玄関から水が一気に流れ込んできた。
「まずい。逃げ場がない」
とロビンスは思ったが、叫び声を上げることが出来なかったという。
彼はベッドルームに飛び込んで息子を抱いて、妻に向かって「起きろ!」と叫んだ。妻が悲鳴を上げたときには水は腰の高さに達していた。ロビンスは息子を高く持ち上げたが、水位は容赦なく上昇し、ついにロビンスの口の位置にまで達した。
部屋の中を必死に泳ぐ妻に、屋根裏のロフトにはい上がるように指示し、息子を引き上げさせた。浮かび上がった家財道具の残骸の中から、ミルクを探し出した。猛烈な風は屋根を浮き上がらせ、水位はどんどん上昇した。
数時間後、水の流れは止まり、水面には細波すら立たなくなった。もちろん車の往来もなく、いつものように道路で遊ぶ子供たちの声も聞こえてこない。住宅街は異様な静寂に包まれた。
今度は、灼熱の太陽が照りつけ、気温がどんどん上昇した。屋根裏はまるでサウナのようだった。自宅前の下水道からは汚水が噴き出して、悪臭を放っていた。
「このままでは一家全員餓死するか、衰弱死する。息子だけでも何とか助けたい。誰か助けは来るのだろうか。いや、この地域は一番後回しだろう。この黒人居住区は・・」
ロビンスの頭の中にあったのは、この国の抱える「負の歴史」だった。彼は高校生に全米最大の黒人の人権団体「NAACP・全米黒人地位向上委員会」の活動を手伝ったことがある。以来30年間、南部に色濃く残る人種差別問題を忘れた日はなかった。
「公民権運動は過去のものではない。この国の社会構造や人権意識など全く変わっちゃいないんだ」
1階の玄関ドアのあたりを「ゴツン・・・、ゴツン」と2度叩く音がした。
「おーい、ここだ。ここに3人いるぞ!助けてくれ」
ロビンスは力の限り叫びながら、天窓から屋根にはい上がった。ボートのエンジン音は聞こえてこない。ロビンスは屋根に這いつくばって、濁った水面を覗き込んだ。その瞬間思わず眼をつむって顔を背けてしまった。
目の前に浮かんでいたのはボートではなく、漂流していた黒人女性の遺体だった。首が不自然にねじ曲がったその女性は目を見開いて、ロビンスをにらみつけているかのように見えたという。
体内に発生したガスでパンパンにふくれあがった彼女は、そよ風に流されながらロビンスの家のガラスに頭をぶつけていた。
ロビンスは、ヘリコプターの音が聞こえるたびに、息子を抱えて屋根裏部屋から屋根に飛び出し、照りつける太陽に子供をかざした。赤ん坊を見れば助けに来るのではないかと思ったのだ。
そんなロビンスの淡い期待はむなしく打ち砕かれた。沿岸警備隊のヘリコプターは轟音を立てて、ロビンス一家の30メートル上空を通過していった。朦朧としながら空見つめる息子の顔を見て、胸が張り裂けそうになった。
「お前だけはお父さんが絶対に助けるからな」
ロビンスは、胸に抱いた息子に何度も語りかけたという。
当時ニューヨーク支局の特派員だった私はカトリーナ直撃の翌日、8月30日にニューオーリンズに入ることが出来た。一年前に訪れたときには、街はディープサウスの文化に惹き付けられた観光客で一杯だった。ジャズの音色や、スパイシーなケイジャン料理、美しい建築物、そしてカナダから滔々と流れてくる大河ミシシッピ川。買い物やハネムーンではなく、文化を堪能する旅行者には確かに魅力的な町だった。
我々TBSの取材クルーがヘリコプターで上空から撮影すると、ニューオーリンズの市街地の80%が水没していた。巨大な湖に民家の屋根だけが浮かび、大勢の市民が手を振って助けを求めている。屋根には「ヘルプ!」「ここには病人がいる」といった文字が書かれている。
車で市街地にはいると、超大国アメリカとは思えない光景が広がっていた。ダウンタウンの避難所となったコンベンションセンターの電気の消えたホールには、何千人もの被災者の目が光っていた。一部の例外を除いてはほとんどが黒人だった。
人々はマイクに向かって
「夜になると発砲音が聞こえ、レイプされていると思われる女性の叫び声が響き渡った」
「水没した住宅街ではアリゲーターが死体を食べているんだぞ!」
と訴えた。
水洗トイレも流れないためトイレ周辺には糞尿が溢れかえり、ホールで用を足す者も出てきた。それに腐敗した食料も加わって、近代化されたコンベンションセンターには凄まじい悪臭が充満していた。
水も食べ物も底をつき始めている。路上には太った黒人男性の遺体が放置され、その脇で生きているのが死んでいるのかもわからない年寄りが、ぐったりと横たわっていた。人々はそれを跨いで歩いていた。
「アメリカ合衆国は我々を見捨てた。ルイジアナ州は壊滅状態だ。」
避難所の人びとは飢え始め、生存競争を始めた。しかし武装した州兵や警察官たちが乗り込んできて、スーパーから食料を略奪しようとする少年たちにまで銃口を向けた。橋を渡って集団で逃げてくるニューオーリンズ市民に、隣接する町の警察官が発砲し、追い払うという事件も起きた。
黒人市民達が「政府は被災者を棄民として扱っている」と絶望するのも無理もない光景が、町中のいたる場所で展開されていた。
ロビンス一家が救出されたのは31日の夕方、サウナ風呂のようになった屋根裏に閉じこめられてから約60時間が経過してからだったという。
助け出してくれたのはモーターボートに乗った若い男だった。彼は警察官でも、消防隊員でも、沿岸警備隊でも、米軍兵士でもない、自主的に救助活動を行っていたボランティアだった。
ロビンス一家3人を高速道路のインターチェンジにボートで連れて行くと、男は
「高速をずっと歩いていけば誰かが助けてくれるはずです」
と言い残して、住宅街に消えていった。
その後、ロビンスたち一家3人は、救援を求めて何十キロもさまよい歩いた。民間救護所に行って「食べ物を分けてくれ」と言うと、冷たく突き放された。中には「ここは白人専用だ」と言い放った救護ボランティアもいたとロビンスは言う。一家は人種差別と、無様に混乱した国家の危機管理に翻弄されることになったのだ。
ロビンスは隣の都市の知人宅に身を寄せて妻子の安全を確保すると、黒人被災者に対する人種差別の調査にとりかかった。ホテルや友人宅を転々としながら連日朝から晩まで避難所を回って、被災者の話を聞いて回った。訴訟を起こす準備を開始したのだ。
「助けを待っている人の95パーセントが黒人だった」
とロビンスは語る。
彼が調査中に一番の驚いたのが、被災者たちが行き先も告げられず次々と飛行機で受け入れ先の各都市に送り出されていたことだ。ヒューストンやダラス、アトランタという近隣都市ならまだ良いが、カリフォルニアやニューヨーク、中にはアラスカ行きの飛行機に乗せられる者もいた。
「君には信じられないかもしれないがニューオーリンズの黒人貧困層は市外に出たことすらない人がほとんどだ。彼らは怖がっていた。しかし、まるで荷物をシッピングするかのように、無理矢理送り出されていた。悲惨な光景だった」
ロビンスには「被災者用住宅を用意している」という口実のもとに、黒人貧困層を強制隔離しているように映ったという。
私は「カトリーナから一ヶ月後の復興への努力」を取材するために再びニューオーリンズに入った。ロビンスと連絡を取り、翌朝いっしょに食事をしようということになった。
そこは白人富裕層が住むジェファーソン郡の洒落たカフェだった。ニューオーリンズ市内の貧困街はヘドロに飲まれた状態のまま悪臭を放っているが、この地域はいち早く復興して、被災前の姿に戻っていた。
混雑した店内で、薄汚れた服を着たロビンスがベーコンエッグを注文すると、20歳くらいの若い女性店員は「朝食は終わりました」と素っ気なく告げた。
「何か残っているかい?ニューヨークの友人に朝食をご馳走するんだ」
ロビンスが言うと、ブロンドの女性店員は作り笑いを浮かべて両手を広げてこういった。
「知らないわ!」
「そこにマフィンがあるでしょう。それをください」
ロビンスは顔をしかめると食い下がった。
「知らないわ!」と店員は目を見開いて、オウムのように繰り返した。
ロビンスは苦笑いを浮かべて振り向いて、「この店は出よう」と言った。後ろに並んでいた白人の客が朝食を注文すると、彼女はにこやかに受け付けた。
貧困街の家を失った黒人とアジア人が無線飲食をすると思ったのだろう。結局、我々は別のチェーン店でドーナツを袋一杯買い込んで、外のテラスで食べた。
ロビンスは両手を広げて、
「これが現実さ。珍しいことじゃない」
と申し訳なさそうに小さな声で言った。
「黒人と白人は死んだときも別々だということも知っていますか?この町には黒人専用、白人専用の葬儀場がある。黒人専用の葬儀場ではカトリーナによる死者の葬儀が一日10件のペースで行われています。順番待ちの状態なんです。公民権運動が終わって時代は変わりましたが、現実は何も変わっていない。いまだに我々は黒人として生まれ、黒人として死んで行くのですよ。」
ドーナツを口一杯に頬張ったロビンスの眼鏡の向こうの大きな目に涙がにじんでいた。
アメリカ合衆国の人種差別は、決して過去の歴史ではない。オバマ大統領がいま最優先課題として向き合っている空前の規模の景気対策の向こう側には、貧困に喘ぐスラム街の黒人達がいる。彼らは経済危機によって、さらなる苦境に立たされているのだ。
オバマは「我々を分け隔てた壁は消える」と演説した。しかし黒人社会の一部として苦難の歴史を継承してきたオバマこそが、人種問題解消の困難さを熟知しているはずである。「自由の国」という蓋の下に隠されてきた人種問題が、自らの大統領就任と経済危機によって再浮上して、目の前に大きな壁となって立ちはだかることも、予測しているはずだ。
オバマはこれに真正面から取り組むことを宣言している。我々メディアの者たちも「ポスト・レイシャル」などという耳当たりの良い言葉に酔うのではなく、自由の国アメリカが抱える矛盾を視聴者に伝えていかねばならないことは言うまでもない。
元ニューヨーク支局 竹内明