平川克美 3・11後の日本へⅣ
2011/05/01
~3・11から~
仕組みってただの基準だから、一応の基準はあるんだけど、実際の運用はこうやっていますよということを言えればいいと思います。
自分の親を助けてあげられたかと。自分の隣人で失業した人を助けてあげられたかと。とりあえず金を貸してあげたのか、ということが大事なんです。直接の利益にはならないし、効率的なやり方でもないけれど、先ず自分ができる身の回りのことをやる。それができないやつが偉そうなことを言ってもそれは信じるべきではないってことですよね。そこが危ないところで、人権派とかヒューマニストが陥りやすい欠点ですよね。


一方で、新自由主義的というか、資源を強者に集中して、効率を高めようという主張がありますね。ビジネスマンはもとより、政治家にも効率主義みたいな考え方をする人が多いと思います。この人たちはどっちかっていうと、弱肉強食の論理の人だから、金のことしか言っていないんですね。金のことしか言っていないというのは、ようするに金のようなもので計量できるものにしか価値を置いていないということです。それをいかに効率的に、より多く持つことが幸せなんだという論理ですよね。
いわゆる都市圏構想というんですか。大阪都、中京都、東京都、どこかにリソースを集中させようという考え方。そしたら二重行政がなくなって効率的に動くよという。確かにその通りなんだけど、今問題になっていることは東京に人が集まりすぎていることでしょう?分散させたいんでしょう?だったら逆じゃない。もっと細かく割って、それぞれが特色を持ってそこにUターンしていくという形を作らないといけないはずなのに、効率だけを考えて、真ん中に集めて、つまり一番強い、一番生産量が多いところにリソースを集中させる。
これはビジネスの論理なんだよ。だからビジネスマンが政治に入ってくると、必ずビジネスの論理をそこに適用するから、効率化、マネジメントということを言っちゃうわけですよ。これは社会の設計にとっては最悪なんです。政治とビジネスは全く別です。ビジネスの価値観を僕は否定しないです。僕はビジネスマンだから。でもビジネスの論理が通じる世界というのは人間の活動の中でおそらく10%とか、20%ぐらいの領域です。会社っていうのは、どこまでいっても利益を追求する場所であるわけで、その意味では弱肉強食です。ここに変なヒューマニズムをいれたら、ビジネスはできないし、公平性を保てない子どもの論理になってしまう。博打の世界。それはいい。博打でやれよと。でもそれをほかの残りの80%に適用するな、と。「分けろ」ということなんです。
教育と医療と介護、宗教に関しては、いわゆる等価交換の論理をいれるなと。もともと等価交換ではないものなんです。

―わけるという考え方・・
そうです。そこを僕ははっきりさせたい。僕は、ニコルさんみたく自然に囲まれて生きるということに憧れは持ちますがしたいとは思わない。こういうごちゃごちゃした都会で生活したい。そこで生きていることの実感を得られるし、どこかにこもって晴耕雨読というわけにはいかない。
それは何でなのということを理論化しないといけない。そうでないと僕みたいな発想の人は必ずエコロジーの方に行っちゃうから。でもエコロジーはいいよという考え方とグローバリストが言っていることは、僕は全く同じものの裏表だと思っています。
そうじゃないんです。さっき言った「とりあえずできることしましょう」という発想は、いま自分の立っている場所で、まず身の回りでできることをやるというものです。これを全部捨てて新天地には行なかないよと。なぜなら僕にはそこへの責任があるから。そこでやっていることに責任があるからそこでやりましょうと。前にも言いましたが、今自分がいる場所は、自分たちが望んで作り上げてきたことの結果なんです。
ロジックとしてだけ見れば、いま自分が立っている場所に対する責任はないんですよ。だけど、責任があるというふうに考えられるのが人間なんです。それが俺の責任だと言えることが人間を素晴らしいものにしていると僕は思うんです。本来自分の責任ではないものを、これは俺の責任だから俺が引き受けるよと言える人がたくさん出てくれば、ものすごくよくなると思います。一歩一歩しかできませんが、それをやりたいわけです。
自分がやったことではないのに自分の責任として引き受けるという考え方は日本人独特なんですよ。アングロサクソン系の人は、自分がやったことでも人のせいだと言いたがるけど(笑)。交通事故でも絶対謝るなというでしょ?でも、日本人はつい「すいません」って言っちゃうんですよね(笑)。
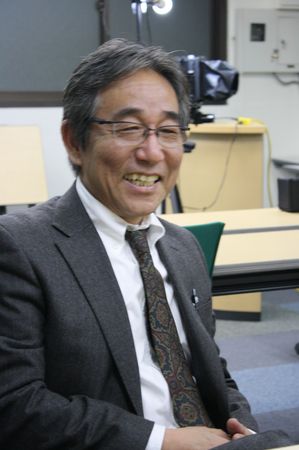
自分のせいではないのに「自分に責任があると思える」ことがそうさせる。そういうフィクションを信じられるメンタリティーが日本人にはわりと伝統的にあるんです。
というのは貧しかったから。貧しい社会がやっていくにはそういうメンタリティーを皆で共有しないと・・・。貧しいのにそこで富の偏在をさせちゃうと、本当に片っ方が死んじゃうし、富をたくさん取ったほうの人も働き手がいなくなっちゃって逆に困る。だからそういう全体適合の生存戦略が働くんですね。だから貧しいということはとってもいいことだったんだよ。富めるところから出発するとなかなかそういう発想にはならない。

―私の周りの友人は、「お金持ちになりたい」とか「贅沢な暮らしをしたい」とは言わない。「そこそこの生活が送れればいい」と言います。年を取った時、家があって、ご飯が食べられる生活ができて、あと、できれば家族に支えてもらえるような状況であれば万々歳だよねという人が主流なんですよ。
それは希望だよね。それはものすごい希望なんですよ。とりあえず雨露をしのげる家があってというのはものすごい希望。それなのにそのことを、日本人は内向きになったとか言う人が出てくるわけです。そういうのは、全く人間理解において浅薄だとしかいえません。ビジネスの最先端でやっている人だとか政治家が経済成長だなんだと言っている間に、多くの人々は、そういう生存戦略に従って、自分はこのくらいでこんな感じでやっていけばいいんだと、生活水準のハードルを無意識的に下げたんですよ。下げて、やり始めている。そのほうが知恵が働いているんです。だから黙っていても大丈夫です。そういうフィードバックが働く社会はいい社会なんです。
なんか日本はだめだと言いたがるんだけど、僕らはこんな日本でよかったねと言っています。

平川克美(ひらかわ・かつみ)
1950年東京生まれ、1975年、早稲田大学理工学部機械工学科卒業。
渋谷道玄坂に翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを設立、代表取締役となる。99年、シリコンバレーのBusiness Cafe,Incの設立に参加、現在、株式会社リナックスカフェ代表取締役。
2011年より、立教大学ビジネスデザイン研究科(MBA)特任教授。
著書に「反戦略的ビジネスのすすめ」(洋泉社)、「株式会社という病」(NTT出版)、「経済成長という病」(講談社現代新書)、「移行期的混乱」(筑摩書房)。
内田樹との共著に「東京ファイティングキッズ」(柏書房)、「東京ファイティングキッズ・リターン」(バジリコ)などがある。
バックナンバー
| タイトル | レス | 最終更新 |
|---|---|---|
| 西川美和 過渡期を生きる女性たち | 0 | 2012/11/26 18:36 by WEB多事争論 |
| 坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」 | 0 | 04/03 17:55 by WEB多事争論 |
| 戦後66年、原発、ニッポン。 | 2 | 08/11 19:33 by WEB多事争論 |
| 平川克美 3・11後の日本へ | 0 | 2011/04/28 13:15 by WEB多事争論 |
| 「レオニー」に託すもの 松井久子さん | 0 | 2010/12/15 19:34 by WEB多事争論 |
| 新宿の小さなお店ベルクから | 1 | 2010/10/16 13:00 by WEB多事争論 |
| 内田樹 メディアの定型化に | 4 | 2010/10/29 04:57 by リッキー |
| 藤原帰一 参議院選挙を前に | 2 | 2010/07/11 21:07 by 長文 |
| 拡大版 沖縄・慰霊の日 | 1 | 2010/07/06 00:33 by くらりん のぶこ |
| それがたとえ1ミリでも | 0 | 2010/05/12 15:40 by WEB多事争論 |
| みうらじゅんさんからの贈り物 | 0 | 2010/03/02 20:16 by WEB多事争論 |
| 「筑紫哲也との対話~没後一周年」から Ⅰ | 0 | 2010/01/23 13:20 by WEB多事争論 |
| 2010年のテレビに | 1 | 2010/01/14 20:17 by whoot |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(III)」 | 2 | 2010/04/04 08:48 by 長文 |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(II)」 | 0 | 2009/09/30 23:59 by 藤原帰一 |
| 「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」 | 0 | 2009/09/26 10:00 by 藤原帰一 |












