戦後66年、原発、ニッポン。Ⅳ
2017/08/14
~新しい場を作ろう~
(金平)
さて、今後の話で言えば、エネルギー環境会議とか、あるいは賢人会議とかが経産省の中に出てきていますが。
(飯田)
賢人会議は肩透かしになりましたが、ただ今度は経産省が、新しいエネルギー基本計画を作ろうとしていますよね。


(金平)
それも原発維持が前提として進められているという。
(飯田)
そうです。
(金平)
このことについて、僕らはどういう教訓を汲み取っていかなければならないのか。原発維持、推進を進めようとしている人たちにとっては、そんなものは考慮する必要もないということなんでしょうか。

(飯田)
彼らにとってはそうみたいですね。原子力推進の御用学者の人たちも、今、めっきりメディアに出なくなって、それこそどこかの番組に出た時に原子力ムラの人が言っていたのは、「みんな、この暴風が過ぎるのを首をすくめて待っているんですよ」と。みんな、考え方は全然変わっていないと聞きました。経産省は変わっていないまま表に出そうとしていますし。だから、あの人たちを変えていくのはなかなか大変なので、新しい場を作っていくしかないんじゃないかと思うんですよね。
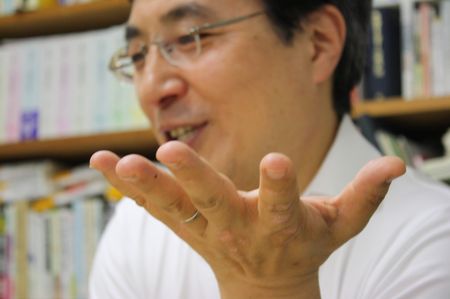
一方で、NGO関係のメーリングリストに「密室で決めるのはやめてください」という署名活動をするとありました。それを見て、そんな情けないのやめませんかと言ったんです。
相手にもう正当性がないことが明らかなのに、こちらから「お願い・下さい」モードで言ったら、向こうに正当性を持たせるだけでしょ、と。我々自身でやりましょうよという話です。
いま、自然エネルギーの普及に関し、この前官邸に呼ばれた小林武史さんらと、我々で場を作ろうという話をしています。また、長野県の阿部知事と先週一緒だったんですけど、私自身も参加するから長野県でプラットフォームを作ろうという話をして、ほかの知事にも呼びかけようと。大阪の橋下知事や神奈川県の黒岩知事はノリがいいから、タイミングさえ合えば来てくれるかもしれない。そういう新しいデファクトを作っていくしかないという気がしますね。古い人たちは横に置いておいて。

(金平)
抵抗も大きいでしょうね。
(飯田)
大きいでしょうね。でも、ここは本当に、昔ながらのオーソドックスなもので型をはめようとする経産省に対して、そうじゃない場を作る、311後の最初の正念場ではないかと思うんですよね。さすがに、原発再稼動という海江田宣言は通らないでしょう。首長であの宣言を飲む人は誰もいないと思うんです。あんな馬鹿なことやっている人には早く退場してもらえるような構図を作らなきゃいけないと思っています。今、けっこう、自民党の中の空気も変わってきつつありますしね。
(金平)
僕は河野太郎という人の動きを注目しているんですけどね。
(飯田)
河野さんは、今回、自民党エネルギー政策議連を作ったじゃないですか。で、共同代表が西村康稔議員なんですよね。西村さんを入れたというのが、河野さんの、なかなか遠謀深慮というか、バランス感覚というか・・・絶妙ですね。西村さんは、軸足は地下議連とかあっちのほうにあるんですが、でも新しい動きにもしっかり噛んでおきたい、という感じでしょうか。大局観と現実感覚の人選だと思います。
(金平)
言葉のレベルがまったく違いますからね。
(飯田)
まったく違いますよ。そのことによって、河野太郎議連が、今、自民党の中でおそらく一番力のある政策議連になってきているんですよね。あと民主党も、小沢さん自身はともかく、小沢さんの周辺の人たちは、川内博史さんとか福島伸享さんとか、原口一博さんとか、筋金入りの改革派が固めているので、民主党の中もこれからけっこう変わっていく可能性がありますね。

(金平)
でも民主党の運命もわからなくなってきましたけどね(笑)。
さて、あまりね、語られていない文脈の話を一つするんですけどね、僕は今度のことで、さっき仰っていたような、日本的な風土というか、知の風土の弱さとか、そういうことももちろんあると思うんですけども。やっぱり、戦後の歴史的な経緯というものをきちんと検証しなくてはいけないという思いがあります。
実はね、僕らが今、本当は考えなくてはならないことというのは、もう一つの虚構じゃないかと。それは、「原子力の平和利用」という問題です。

(飯田)
はい、まさに、そうですね。
(金平)
僕は、その部分にとても興味があって、アメリカにいた時はずっと調べていたんですけどね。1953年に、アトムズ・フォー・ピース(平和のための原子力)という、有名な、アメリカのアイゼンハワー大統領の国連演説がありますね。あれは実は、冷戦下の中での、原子力エネルギーのイニシアチブをどちらが取るかという非常に緊張した場面で、アメリカがあの「アトムズ・フォー・ピース」で勝つんですよね。それであちこちに原子炉をばらまくわけです。イラクとか、ヨーロッパとか。それで平和攻勢をかけるわけですよね。
ところがですね、現実的には原子力の平和利用というのは、僕は今考えてみるとー当時の人ももちろんわかっていたと思うけれどー政治的には原子力を平和のツールとして使おうという話は一定の意味はあるかもしれませんが、技術論的に言うと同じものですよ。
(飯田)
そうです。そうです。

(金平)
当時、第五福竜丸事件というのがあって、それをきっかけに、日本の中で、原水禁運動が活発になり、反核感情がものすごい高まりを見せますよね。広島、長崎、第五福竜丸とあって。
でもその後の色んな経緯を見ると、読売の正力松太郎と、まだ一介の議員だった中曽根が動きますね。アメリカの、今でいうCIAのもものすごいお金をつぎこんで、日本の反核運動を抑えにかかるんですね。この時、正力の懐刀だった柴田秀利という人間は、「毒をもって毒を制す」と言ったんですね。杉並の主婦が始めた原水禁の運動を抑えるには、毒をもって制すしかないんだと。そして、タダで原子炉をプレゼントするんですよ。茨城県東海村に実験炉として。
そういう経緯を踏まえて、その後をずっと見ているとですね、あの大江健三郎が「ヒロシマ・ノート」を書いた5年後ぐらいだと思うんですけど、「原子力の平和利用は素晴らしいことだ」と。今でこそ「ヒロシマからフクシマ」へ、なんてことを言ってますけどね。「僕は核兵器は全面的に反対だ。核兵器を作らないってことさえOKならば、どんどん平和利用で原子力を使おうよ」というようなことをあちこちで言っている。大江健三郎でさえそうです。知識人の責任とか、言論人のアイデンティティーというのかな、ある種の一貫性っていうことを、きちんと責任もって言うためにはね、そこのところは避けて通れないところだと思うんですね。
(飯田)
高木仁三郎さんはまさにそれを両方やっておられましたよね。
当時、政治は中曽根で、政府の中に入りなおかつメディアも商業も仕切ったのが正力で、もう一つ、仁科(芳雄)さんが悪かったんだと思うんです。
(金平)
理研の?
(飯田)
はい。原子物理学者の。彼は、「原子爆弾を落とされた日本にこそ、原子力を正しく平和に利用する権利がある」と言っているんです。もちろん原子力は夢だとか、鉄腕アトムだとか、政治でゴリゴリ来た話とありますが、アカデミズムの世界では、仁科さんのこのロジックが腸ねん転を起こさせたんですよ。そこから日本人は、どの角度で切り取っても、庶民は正力にだまされ、アカデミズムは、「自分たちこそが」と、ナイーブなある種の発展主義の方に化けてしまいですね。

(金平)
だけど、それに対しては、原子力の平和利用がおかしな方向にいってはいけないと、物理学者の武谷三男さんたちが、「原子力三原則」※⑥で、一生懸命歯止めをかけようとしたじゃないですか。
(飯田)
でもそれに対して仁科さんが、発言で、結局原子力を受け止めてしまうというか、ジョン・ダワーのように「抱きしめて」しまうんですね。
(金平)
でもいくらなんでも、原子力を抱きしめちゃったらどうしようもないわけで、敗北を抱きしめるどころじゃないと思いますよ。
(飯田)
結局あれです。広島には原発反対運動がほとんど存在しないですよね。長崎もそうですけど。
(金平)
それがね、本当に象徴的な話なんですが、原水禁運動とか被団協とかありますが、被団協の中で反原発はタブーなんですって。これはものすごくねじれた論理でね、原発労働者と原爆で被曝した人を同じにしないでくれと。
ところがさすがに今はこんなことがあったんで・・・。
福島県の被団協、これはとっても嫌な話なんですが、昔は被爆者ってなかなか仕事に就けないとか結婚差別とか色んな問題があって、福島県に流れていって原発労働者になったりしているんですって。そういう構図があって今回の事故があった。
(飯田)
まさに二重被曝ですね。

(金平)
そうです。福島県の被団協、被爆者たちは、今度こういうことがあったんで「とんでもない」と。「なんでこんなことになっちゃたんだ」と、自分たちのこれまでのポリシーに対して、やっと見つめなおそうとなったんですね。その時に何が起きたかというと、広島の被
団協というのは、電産とか、つまり民主党系の組合というのは電気産業が多かったりして、「それはやられると我々の立場がなくなる」という形で、福島県の被団協に対して「余計なことを言うな」と言っているらしいです。それで情けない話ですが、原水禁世界大会がことし8月にありますが、それに先立って、福島県で原水禁系のプレ大会があるんです。それはなぜかというと、広島でやると押さえ込まれちゃうから。
(飯田)
なるほど。
(金平)
この期に及んでこういうことが起きているというのが、もうなんという・・・。
(飯田)
どこまで行ってもムラ社会ですね。
※⑥物理学者、武谷三男らが提唱した原子力平和利用の三原則「自主・公開・民主」。
飯田哲也(いいだ・てつなり)
1959年、山口県生。京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。神戸製鋼、電力関連研究機関で原子力R&Dに従事した後に退職。現在、NPO法人環境エネルギー政策研究所所長。自然エネルギー政策研究と実践で国際的に活躍する。著書に『自然エネルギー市場』(編著 築地書館)、『北欧のエネルギーデモクラシー』(新評論)、『原発社会からの離脱』(講談社現代新書)など。
(聞き手)
金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。
バックナンバー
| タイトル | レス | 最終更新 |
|---|---|---|
| 西川美和 過渡期を生きる女性たち | 0 | 2012/11/26 18:36 by WEB多事争論 |
| 坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」 | 0 | 04/03 17:55 by WEB多事争論 |
| 戦後66年、原発、ニッポン。 | 2 | 08/11 19:33 by WEB多事争論 |
| 平川克美 3・11後の日本へ | 0 | 2011/04/28 13:15 by WEB多事争論 |
| 「レオニー」に託すもの 松井久子さん | 0 | 2010/12/15 19:34 by WEB多事争論 |
| 新宿の小さなお店ベルクから | 1 | 2010/10/16 13:00 by WEB多事争論 |
| 内田樹 メディアの定型化に | 4 | 2010/10/29 04:57 by リッキー |
| 藤原帰一 参議院選挙を前に | 2 | 2010/07/11 21:07 by 長文 |
| 拡大版 沖縄・慰霊の日 | 1 | 2010/07/06 00:33 by くらりん のぶこ |
| それがたとえ1ミリでも | 0 | 2010/05/12 15:40 by WEB多事争論 |
| みうらじゅんさんからの贈り物 | 0 | 2010/03/02 20:16 by WEB多事争論 |
| 「筑紫哲也との対話~没後一周年」から Ⅰ | 0 | 2010/01/23 13:20 by WEB多事争論 |
| 2010年のテレビに | 1 | 2010/01/14 20:17 by whoot |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(III)」 | 2 | 2010/04/04 08:48 by 長文 |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(II)」 | 0 | 2009/09/30 23:59 by 藤原帰一 |
| 「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」 | 0 | 2009/09/26 10:00 by 藤原帰一 |












