戦後66年、原発、ニッポン。Ⅴ
2017/08/15
~「地域」と「世界」と「アート」~


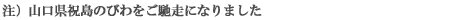
(金平)
さて、明るい話もしないと(笑)。今、日本でも、ようやく、フィード・イン・タリフとか新しい動きが出ていることは確かですよね。背景にはもちろん電力自由化の流れがあって、もちろん思惑はバラバラですけど。これまでの幕藩体制をずっと311以降も維持できるみたいなことというのは、むしろ利用者の側が許してはならないことですよね。そういう中で何を目指していくのか、飯田さんなりのお考えを聞かせてください。
(飯田)
一番は、とにかく、社会全体の政策を変えないといけないんですが、これはこれでナショナルなアジェンダなので、なかなか大変なんですが、やっぱり地域地域でやっていくということが非常に重要だと思うんですね。
(金平)
地域地域というと、地産地消とか地方への権限委譲みたいなところに行っちゃいますけど・・・。
(飯田)
地産地消は、今度はまたナイーブすぎますね。ちょうど先週も、デンマーク・サムソ島の、サムソエネルギー環境事務所ゾーレンハーマーセンさん※⑦を山口県の祝島※⑧に連れて行ったんです。結局、それぞれの地域で起きていくことはグローバルに照らし返すことができて、しかもそれはリアルにつながっていって、日本史と世界史を同時に作り上げていくんですよね。

しかも、原発反対運動だと、例えば原発を地域で食い止めるという、勝つか負けるかみたいな苦渋の時間を祝島も30年過ごすわけですけど、自然エネルギーを作っていくというのは、1年とか短いサイクルで何かひとつが完結して、何か完結することによってみんなが成長して、しかもそこに参加する人がまた一回り増えて、で、また次のサイクルになると、またもう一回り大きくなってまた成長するという、プラスのスパイラルが起きる。しかも世界ともつながっていく。


そういうことが日本中の色んなところで次々に起きてつながっていくというそのプロセスが始まると、また、それが、国全体の政策にも影響を与え、社会が変わっていきますし、世界ともつながっていくと。それが自然エネルギーの小規模分散型エネルギーを軸にすれば可能になるんですよね。そういうプラスのポジティブサイクルをどう地域の拠点から作っていくのか。
これまでのように補助金をどかんと地域に垂れ流すと、回らない風車だとかコンサルタントが入り込むだけとかになるんですが、地域の人々が自分たちの地域の中で二本足で立って、自分たちで新しいものを作りあげていくというプロセスが、かなり今、リアリティーをもって始められるようになってきていると思いますね。
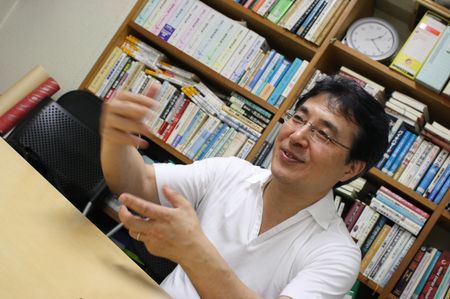
(金平)
なんといいますかね、そこに対しメディアの役割があると思うんですが、そういう素敵な試みがあるとか、そういうことについて、PRがすごく大事だと思いますよね。そういう流れは追い風になっていると思うんですね。例えば、交付金なんかで作ったハコモノが一体何の役に立っているのかということは、皆が思っていると思いますしね。ところが、これまでどおりのやり方がいいんだというふうに戻ってしまうと、なかなか変わるきっかけがない。
これから先のことを考える上で、何かヒントがあるんじゃないかと思うのは、さっきのデモではないんですが、「楽しくやる」ということじゃないかと思いますね。まなじりを決して「勝つか負けるか」というやり方は、時代遅れだし格好悪いですよね。そうじゃないやり方というのがあると思っていて。
例えば、そんなに原発やりたいの?という人たちはその人たちの顔をさらしちゃうとか、この人たちが原発好きでたまらない人たちですと紹介するやり方とかね。糾弾するんじゃなくて、色んなやり方があると思うんですよ。でも日本人ってそれが下手ですよね。ユーモアがないのかな・・そういうところがこれからとてもカギを握っていくような気がします。それはたぶん、文化の力だと思います。文化。

(飯田)
そうですね。
(金平)
だってヨーロッパでそういうのを支えているのは食べ物とか音楽とか暮らし方。つまり文化です。
(飯田)
まさにそうです。
(金平)
それには勝てないですよ。いくら物や金をぶら下げられたって。
(飯田)
シンボリックな風景でいうと、日本とヨーロッパ、特に北欧って、まったく対照的で、日本の田舎って、まず駅に降りると、パチンコ屋とプリクラとシャッターとサラ金とコンビニしかない(笑)。

で、その寂れた町を通っていくと御殿のような役所がある。で、その御殿のような役所の外見は近代的というか一応きれいなつくりなんですけど、中に入ると、戦前の役場そのもののような大部屋で、雑然と書類がうずたかく積み重なっている。北欧だと、そのちょうど真反対。駅前、中心は古い景観を維持しつつも非常にモダンなディスプレイがあって、人のにぎわいがあって、役所は古い建物だけども、中に入ると暗黙知と形式知をきちんと使い分けた知的空間が作ってあるわけです。一人ひとりは個室ですし、でも閉じこもる個室ではなくてガラス張りで見えるし、ちょうど視線の辺りはスリガラスになっていてお互いの視線は気にならない空間になっています。しかも真ん中には大机があって、午前10時とか午後3時とかには、当番でかわりばんこで作ってきたケーキを食べながら皆で雑談をしながらコミュニケーションをとる。それでまた個室に戻り集中して仕事をする。まったく逆なんですよ。社会空間のあり方が。
いわゆるモノとかカネではない、クリエイティブなものであるとか、アートなものとか、そういうものがこれからの社会を築いていくんだという共有感覚があって。けっこうシリコンバレーもそれに近いらしいですが、夜バンドでサックス吹いている人に話しかけて、明日、どこどこの会社の社長に会うんだけどと言ったら、それ俺だとか(笑)。

そういうようなクリエイティブとこれからの知識社会とアートというのはすごく一体なものだと思います。日本はもう一段そこに向けて脱皮しないといけないという気がします。

※⑦デンマークのサムソ島で、自然エネルギー100%構想を中心となって実現した
※⑧山口県の瀬戸内海に浮かぶ人口500人の島。対岸わずか3.5キロの場所に中国電力が上関原発の建設計画を進めていて、およそ30年にわたり建設反対運動を続けている。
飯田哲也(いいだ・てつなり)
1959年、山口県生。京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。神戸製鋼、電力関連研究機関で原子力R&Dに従事した後に退職。現在、NPO法人環境エネルギー政策研究所所長。自然エネルギー政策研究と実践で国際的に活躍する。著書に『自然エネルギー市場』(編著 築地書館)、『北欧のエネルギーデモクラシー』(新評論)、『原発社会からの離脱』(講談社現代新書)など。
(聞き手)
金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。
Re:戦後66年、原発、ニッポン。Ⅴ
2012/01/27
- 投稿者
- 阿部寿
- 投稿日
- 2012/01/27
筑紫哲也さんのことを思い出したくなり、偶然このサイトにたどり着きました。興味深く読ませていただきました。これからも、良質の報道を期待します。
バックナンバー
| タイトル | レス | 最終更新 |
|---|---|---|
| 西川美和 過渡期を生きる女性たち | 0 | 2012/11/26 18:36 by WEB多事争論 |
| 坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」 | 0 | 04/03 17:55 by WEB多事争論 |
| 戦後66年、原発、ニッポン。 | 2 | 08/11 19:33 by WEB多事争論 |
| 平川克美 3・11後の日本へ | 0 | 2011/04/28 13:15 by WEB多事争論 |
| 「レオニー」に託すもの 松井久子さん | 0 | 2010/12/15 19:34 by WEB多事争論 |
| 新宿の小さなお店ベルクから | 1 | 2010/10/16 13:00 by WEB多事争論 |
| 内田樹 メディアの定型化に | 4 | 2010/10/29 04:57 by リッキー |
| 藤原帰一 参議院選挙を前に | 2 | 2010/07/11 21:07 by 長文 |
| 拡大版 沖縄・慰霊の日 | 1 | 2010/07/06 00:33 by くらりん のぶこ |
| それがたとえ1ミリでも | 0 | 2010/05/12 15:40 by WEB多事争論 |
| みうらじゅんさんからの贈り物 | 0 | 2010/03/02 20:16 by WEB多事争論 |
| 「筑紫哲也との対話~没後一周年」から Ⅰ | 0 | 2010/01/23 13:20 by WEB多事争論 |
| 2010年のテレビに | 1 | 2010/01/14 20:17 by whoot |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(III)」 | 2 | 2010/04/04 08:48 by 長文 |
| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(II)」 | 0 | 2009/09/30 23:59 by 藤原帰一 |
| 「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」 | 0 | 2009/09/26 10:00 by 藤原帰一 |












