西川美和 過渡期を生きる女性たちⅤ
2012/12/04
3・11
(金平)
3・11の後、是枝さんは被災地に行って映画を撮られたりしました。それ以外の映像に関わっている表現者の中でも、例えば園子温さんも映画を作りました。3・11は、西川さんの中にはどう残りましたか?
 |
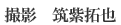 |
(西川)
たぶん、多くの物書き、映画人がそうだったと思うのですが、あんなに無力感を感じたことは無かったです。
そもそも私の仕事は、食べ物を作っているわけでも燃料作っているわけでもないので、あるべきなのかどうなのかわからない、怪しい仕事だなとは思っていましたけれど。

ちょうどその頃、私は今回の映画の脚本を書く時期でした。被災地に行って炊き出しをしている人、体育館で歌う人気歌手や、それを聞いて涙を拭う被災された方達を横目に見ながら、1人でこたつに入って、人と人がののしり合うようなセリフを書いていました。そのバカバカしさといったら無いという。
自分にとってはその仕事しか出来ないわけですけれど、その時は、こんな仕事をしていて何の意味があるのかとつくづく思いました。もっと人と人が絆を結んで大いなるものに立ち向かっていく、というポジティブな作品だったら良かったんですけれどね。
関係性が崩壊してお互い欺き合うというドラマを作るということが、良いのか悪いのか分からないと思いながら、無力感、無能感を心の底から感じました。
でも、復旧した劇場に自分の映画をかけようというなら、被災地に行くのではなくて、机に向かって1行でも脚本を書き進め、しかるべき時期に撮影する事、私に出来る仕事はそれしかない。そう自分を説得しながら仕事を進めました。その結果ちゃんと映画が出来まして、被災地でもかけて頂いています。
ただ、そうやって進めたこと、自分を自分で正当化したことが正しいことだったのかどうかはよく分かりません。何の救援にも行かず机にかじりついて書いた作品がこれだったのかと言われればそうなのかと思う所もありますし、いまだに葛藤が続いています。もっと直接的に震災をテーマに扱った映画に取り組むべきなのか悩む部分もありました。
一方で、1つ励まされた言葉があります。大きな事件や戦争、悲劇というのは、時間を経た後でも、振り返ってゆっくり熟成させながら忘れずに作っていくこと、咀嚼し続けていくことが大切なんだという言葉です。誰かがそう書いていて、私も、そういう気構えで作っていこうかなとは思っています。

(金平)
3・11の後に、例えば官邸前などでデモをする人がいますよね?何か感じることはありますか?
(西川)
私自身は参加したことはありません。デモの必要性だとか効果は当然あると思うのですが、1つだけ思うのは、集団で大きな声をあげるということ、その快楽に溺れそうになることには気をつけようということです。デモをする人にはそういう内省が必要だと思います。映画の現場でもそうなんですよね。集団で大きな声をあげて進んでいくことってある種の快感もあります。生きている実感もあるし。
でも、あることがきっかけでいろんなものが変わっていったりする事もあるし、快感と感じているものが暴力となって人のものを奪ったり、傷つけたり、個人や個性を潰していくということもあると思うので、そうならないようにしてもらいたいなと思います。

(金平)
最後の質問です。僕らはニュースの仕事をしていて、人々に対し、起きている事を知らせたり、いま考えるべき問題について議題設定をしていますが、特に原発事故以降、世の中には、ジャーナリズムの働きやマスメディアの機能に対する不信感が渦巻いています。今のマスメディアやジャーナリズムについて西川さんがお考えになっていることって何ですか?
(西川)
うーん・・・。
(金平)
そんな一般的なこと質問しないでよって感じですか?(笑)
(西川)
そんなことはないです。テレビというメディアは批判される事も多いですけれど、今回の震災については、私はけっこうテレビから知った事実も多いですし、テレビというジャーナリズムでこそ伝えられるものはまだ残っていると思います。又、それに期待したいという思いもあります。
ただニュースを見ていると-今日だから言う訳ではないですが-、筑紫哲也さんがいらした時って、ニュースを見る際、「この人だったらこのニュースをどう見るんだろう」という動機付けを持つことが出来ました。でも今、ニュースに対し、どう受け止めていいのか分からない時に、ニュースを斬ったり分析したり、こういう見方があるのではないかと視聴者に問いかけるアンカーマンがいらっしゃいませんね。それが残念です。
(金平)
わかりました。次にやりたいことは?なんて月並みな質問はしない方がいいですね?(笑)

(西川)
(笑)1作ごとに空っぽになってしまうので、今は原点回帰するというか、「なぜ自分は映画をやりたいと思うのか」というところにもう一度戻りたいと思っています。初めにも言いましたけど、映画に感動し、こんなものを作れたらいいなという思いでやってきましたので、自分を刺激してくれるような作品にたくさん出会いたいです。本もたくさん読みたいですね。
(金平)
頑張って下さい。楽しみにしています。西川さんは、もしかすると、もの書く方に、どんどんいってしまうのではないかと思っていますよ。先ほどの脚本の話ではないですが、書くの楽しいでしょう?
(西川)
楽しいですね。でも、なぜ映画を作りたいかというと、脚本を書く作業って本当に1人の作業になってしまうんですよ。それに対して映画は共同作業なので、人とコミュニュケートしながら作っていくという作業がとても楽しいんですね。だた書いているだけだと人と接触しなくなってしまうので、いいバランスで、映画の現場と物を書くことを続けていければと思っています。

西川美和(にしかわ・みわ)
1974年、広島県出身。大学在学中に是枝裕和監督作『ワンダフルライフ』(99)にスタッフとして参加。02年、『蛇イチゴ』でオリジナル脚本・監督デビュー。同作品で第58回毎日映画コンクール脚本賞ほか数々の国内映画賞の新人賞を獲得。長編第二作『ゆれる』は第59回カンヌ国際映画祭監督週間に出品され、国内でロングランヒットを記録。09年、長編第三作目となる『ディア・ドクター』は第33回モントリオール世界映画祭コンペティション部門に出品、第83回キネマ旬報ベスト・テン作品賞(日本映画第1位)、第33回日本アカデミー賞最優秀脚本賞など数多くの賞を受賞。今年公開となった四作目の長編映画『夢売るふたり』は第37回トロント国際映画祭に出品された。その他小説作品に「ゆれる」「きのうの神様」「その日東京駅五時二十五分発」などがある。
(聞き手)
金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。












