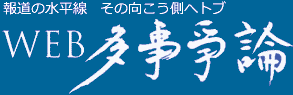戦後66年、原発、ニッポン。Ⅲ
2017/08/13
~知のあり方~
(金平)
あともうひとつは、海外に行っていらっしゃることですね。高木仁三郎さんも、当時西ドイツに行って、外から日本を見るという経験をしています。本物の民主主義というんですか、それを見ると、いかに日本の民主主義が空虚かということがわかりますね。
さらに、僕らが今やっている仕事との関わりからいうとですね、御用メディアとか、御用科学者、御用アカデミズムというんですかね。そのありようというのが、今回の事故を契機にしてこれほどあからさまになったことはないですね。なぜこんなことになってしまったのか、先ほどの空っぽ論議と、もちろんだぶっていると思うんですけどね。
(飯田)
民主主義の問題と同時に「知のあり方」という問題があると思います。これは、御用学者だけの問題じゃなくて、良いことを言っている「真っ当な科学者」も含めて、現実と切り離されている気がするんですね。もちろん、御用学者も問題だし論外なんですけど、真っ当な科学者は、本来、「とんでも御用学者」みたいな人とは学会で戦って徹底的に論戦して彼らの学界的地位を落とさなくてはならないと思うんですね。


(金平)
そうですね。
(飯田)
だけども、そっちはそっちで仲良しクラブになっていてですね、一応、御用学者でも、真っ当な、一応、かぎかっこつきの「真っ当な教授」も、学会や社会的な地位で同じ地位か、むしろ高い地位を得ているもんだから、官僚に「御用学者」として使える価値があるわけです。他方で、例えばかつての「岩波文化人」的な人が、自分は高みにいて、「良くないのは現実が悪いんだ」とか、「お前らが馬鹿だから悪いんだ」みたいな、そういう見下す部分がずっとありましたよね。
ところが、私が一緒に過ごしている、スウェーデンやデンマークの知識人というのは、非常にフラットに民衆の中に溶け込んでいます。でも本来、知識人って、市民的に行動するものです。壁を作らない。
日本では、知のモードが権威主義のまま来てしまっていて、御用学者だけじゃなくて知識人全体が、自分たちの発言と現実を結びつける回路をあまり持てていないのかなと思いますね。

(金平)
なんというか難しいですけど、知識というものとリアリティーというんですかね。
(飯田)
そうです。リアリティー・・・。知識人自身が現実社会を構成する一員として、もっと現実に責任を持たなければならないし、関係性を結ばないといけないんですけど、ちょっと切り離されていると感じます。そこがもっと大きな構図の問題としてある。一部の悪いりんごがいる、というのではなくて、悪いりんごを共存させてしまう日本型の知の世界というか・・。

(金平)
知識って、真理を求めるわけだからぶれないですよね。切磋琢磨するというか、違って当たり前なんで。でも、日本ってぶれるでしょ。
(飯田)
はい。
(金平)
つまりマジョリティー対マイノリティーでいくと、マジョリティーっていう主流派ができてマイノリティーを徹底的に排除しますよね。この間のことでいうと、石橋克彦という神戸大の名誉教授になりましたけど、その人が東大の助手時代に、「原発震災」と言って、原発が地震で大事故を起こす恐れについて告発していました。その時の学会の反応がですね、「石橋というのはどこのチンピラだ、聞いたことないぞ」というようなものだったそうです。また、その石橋論文に関し静岡県議会で質問した議員に、静岡県から委嘱を受けた原子力対策アドバイザーが、ほとんど個人的な中傷に近いんですが、「そんなやつ聞いたことがない」と。「石橋なんてどこの馬の骨かわからない」と。ちなみに当時、静岡県のアドバイザーとしていたのが、これは偶然なんですけど、斑目なんですよ。もう一人が小佐古。
(飯田)
二人とも、東大教授ですよね(笑)。

(金平)
そう。僕はこういう知識のあり方というんですか、つまり権威というものにすがるような、それでマジョリティーがあって、何か異論とか少数意見とか反論に対して聞く耳を持たないと言うんですか。
(飯田)
それは、昔の水俣病の時に、熊本大学の研究班が出したものに対して東大が徹底的に批判したのと、まったく同じ構図ですよね。紙に書かれた事実やロジック、仮説を、虚心坦懐に見るのではなく、まず相手の肩書きとか自分との関係性から見て(笑)。
(金平)
「俺は教授だぞ」と(笑)。「助手なんかの言うことに耳を傾けてたまるか」みたいなものがあるんですか。

(飯田)
ありますね。それは完璧にあります。日本では。それもまた、御用学者により強いですけれど、御用学者ではない人にも強いです。中身ではなく肩書きで見るという。日本独自の学の世界だと思いますけどね。ほかのところも大なり小なりあるでしょうけど、日本ほどひどいところはないですね。

(金平)
6月11日に全国で一斉に行われたデモについても、「まとまろう」とか「がんばろう日本」と言っている中で脱原発を訴えるデモなんて、「なんだよ、勝手なこと言って。みんな困っている時に」っていう、そういうメンタリティー、ものすごい勢いで広まっていると、感じたことはないですか。
(飯田)
構造としては感じますけど・・。まあ、「がんばろう日本」なんて非常に気持ち悪さを感じますけどね。
(金平)
つまり、こんなことがあったのに、なんで、日本の人たちは、マインドシフトができないのかという根底的な疑問があるからお聞きしているんですけれど。
(飯田)
怒らないの?とかですね。
(金平)
そうです。怒らないの?とか。普通こんなにひどいことがあったら、言うでしょ。「なんてことしてくれたんだ」と。「自分たちが住んでいた所に、そんなことが原因で一生住めなくなっちゃうかもしれない」とか、怒りがあったり、「もう原発ごめんだよね」ってならないかなと思うんですけど。世論調査をやると、脱原発を訴える人は徐々に増えてはいますけど、僕はそれにしたって、まだまだ、人々の中の、マインドシフトに対する抵抗感というものを感じます。
(飯田)
ありますよね。地震が起きて2~3週間は、確かにメディアに御用学者があまりにも出ていましたので、メディアの中では311前の空気が続いているんだなと思っていましたけど。でも、4月くらいからだいぶ変わってきたんで、そこは変わってきたのかなとは思っていました。

(金平)
マインドシフトができない理由のひとつに、メディアの人たちの中の、とっても古い枠組みが消えないということがあるかもしれません。例えば、6月11日のデモがあった日、私の番組では中継でデモの様子を伝えました。その後、ほかの民間放送を見ていたんですよ。今日のデモは参加者が2万人超えちゃったし、すごいよなと思って。ところがほかの民放2局が放送した時間は20秒でした。収拾つかないぐらいの人数が集まったデモでしたが20秒。
で、考えたんですよ。つまり、その日の編集長とかデスクって、たぶん40代半ばくらいだろうと。はっきり言ってしまうと、メインではない日は週末シフトになるから、そういう人たちの判断は、「これまでも、土日に市民集会はあったけど、あまり扱っていないよな、デモをやったのだってどうせまたあいつらだよな」という感じ。おそらくそのフレームが、311の後も変わらないままなんでしょう。
4月10日の高円寺のデモもすごかったんですよ。あんなことはなかった。あれは事件だったですね。デモになんか出たことのない人たちが繰り出していって、警察が慌てたんです。参加者が1500人ぐらいだと思っていたら1万5000人くらい来ちゃったわけだから。それはニュースですよね。そしてそれが波状的に広がって、6月11日のデモにつながっていったってことがあるからなおさらなんですけど、この期に及んで20秒というのは、正直、あちゃーという感じでした。
(飯田)
なるほど、そういう状況なんですね。

飯田哲也(いいだ・てつなり)
1959年、山口県生。京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。神戸製鋼、電力関連研究機関で原子力R&Dに従事した後に退職。現在、NPO法人環境エネルギー政策研究所所長。自然エネルギー政策研究と実践で国際的に活躍する。著書に『自然エネルギー市場』(編著 築地書館)、『北欧のエネルギーデモクラシー』(新評論)、『原発社会からの離脱』(講談社現代新書)など。
(聞き手)
金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。