23時の記憶
第3回 2008.9.12 「The Movies」
吉岡 弘行(WEB多事争論編集委員)
「映画・音楽・演劇・絵画・写真など『カルチャー』に関する話題もきちんとニュースとして伝える」
これは「筑紫哲也ニュース23」の柱の一つであり、番組独自のカラーを醸し出す重要な要素だった。
このサイトにコメントを寄せていただいた23人の識者のうち、毎日新聞特別編集委員の岸井成格さんの動画をクリックしてみてほしい。
―――岸井さんはこのように語っている。
「23」では、筑紫さんをはじめとするキャスター陣とスタッフ全員が年に一度、温泉など保養地に一泊して「ブレインストーミング」をするのが恒例だった。
我々は「サミット」とか「おこもり」と呼んでいた。
スタッフ全員が事前に「番組の方向性」「新コーナー」「自分のやりたいネタ」などについてアンケートを書いて「冊子」を作る。
筑紫さんからは「サミットのための若干のメモ」と題した文章を巻頭に寄せてもらっていた。
手元に「98年初島サミットのための若干のメモ」(1998年8月14日付)が残っている。
熱海の沖にある「初島」で開催されたサミットは、番組スタートからちょうど10年目、私がこの番組に参加して体験する最初の「おこもり」だった。
今から10年前のメモの中で筑紫さんはこう記している。
10年という区切りを迎えた番組は、筑紫さんのパートナーが池田裕行(現・TBSパリ支局長)・浜尾朱美キャスターから佐古忠彦(現・TBS報道局政治部デスク)・草野満代キャスターに代わり、新しい方向性を模索していた。
テレビの世界では、「リニューアル」というのは非常に神経を使う作業だ。ある意味、新番組を立ち上げることよりも難しいかもしれない。「23」のリニューアルに2回、夕方のニュースでも2回のリニューアルに深くかかわった私の経験でもある。
うまくやらないと、以前のスタイルやキャスターに慣れた「お客さん」の入れ替え(特に「客離れ」)が生じ、えてして視聴率はいったんは下がるものである。
実際、98年当時「数字」は思ったように伸びていなかった。
そんな当時の状況もうかがえる一文だが、気になるのが「バッシング」という言葉である。
この「バッシング」のひとつに、「23は『硬派なジャーナリズム』を謳いながら、いわゆる『歌舞音曲』など筑紫の趣味に走りすぎている」というものがあった。
ナンセンス!の一言。
私には、ニュース番組を従来のステレオ・タイプなイメージでしかとらえられない人が「嫉妬」もこめて言っているとしか思えなかった。
しかしながら、そういう批判が局内の一部にあったことは事実だし、今でもそんなイメージでニュースをとらえている局員がいることも否定しない。
そんな人に言いたい。新聞をよく読んでごらんと。
ここ数年の「文化面」「生活面」の充実ぶりはめざましく、そんじょそこらのネットや雑誌にはとてもマネできない素晴らしい記事や批評、インタビューが満載されている。
最近、購読する若者が減っているというが、月数千円であれだけ充実した情報が詰め込まれた「新聞」というメディアを再認識してもいいと思う。(私は今でも気になる映画やめぼしい本の記事があるとついスクラップして手帳に挟んでしまう)
さて、筑紫さんがその「カルチャー」の分野で最もこだわったのが映画だった。
年2回の恒例となっていた名物コーナー「おすぎと哲也の映画特集」と不定期で収録・放送される「映画監督との対談」に力を注いだ。
「23」を経理・事務などの面で支え続けている「ムネちゃん」こと棟方美穂さんに、映画監督のインタビューがどのくらいあるかを改めて調べてもらった。これがすごい!
18年半という歴史の重みというか、古今東西の名監督がキラ星のごとくリストアップされているのだ。(*番組の放送年/代表作)
| アラン・パーカー (91年/『ミシシッピー・バーニング』『エビータ』) |
| ジェームズ・キャメロン (91年/『ターミネーター』『タイタニック』) |
| ヴィム・ヴェンダース (91年/『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』) |
| 黒澤明 (93年/『羅生門』『七人の侍』) |
| オリバー・ストーン (94年・95年・2000年/『プラトーン』『JFK』) |
| 宮崎駿 (96年・97年・2006年/『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』) |
| リュック・ベッソン (95年/『二キータ』『レオン』) |
| 北野武 (96年・2002年/『HANA-BI』『菊次郎の夏』) |
| リドリー・スコット (2002年/『ブレードランナー』『ブラック・レイン』) |
| クリント・イーストウッド (2005年・2006年/『許されざる者』『ミリオンダラー・ベイビー』) |
| ジョージ・ルーカス (2005年/『アメリカン・グラフィティ』『スター・ウォーズ』) |
10人ほどあげただけでこの顔ぶれである。
このほかにもハリウッドや中国の監督、日本の岩井俊二、是枝裕和など有望株ら50人以上の監督と対談を行っている。
映画の配給会社の方に聞くと、いつの間にか映画監督が来日すると筑紫さんの「23」に、俳優がやってくると久米宏さんの「ニュースステーション」に声をかけるというのが定着したそうである。
筑紫さんは著書『小津の魔法使い』(世界文化社)で「いつの時代も口実を作っては映画を観ていた。中学生の頃から映画好きが昴じ、高校時代や朝日新聞の地方勤務時代に映画館の『パス』をフル回転させて映画を観た。多忙なワシントン特派員時代は時差を利用して映画館に通った」と書いている。筋金入りの映画ファンなのだ。
実は、私も小学校高学年以来の映画ファンで、筑紫さんの足元にも及ばないが口実を作っては映画を観てきた。
筑紫さんと違うのは、大学で上京するまで地方暮らしだったため、民放各局の洋画劇場が主戦場だったことだ。月・水・金・日の夜は大体、テレビで映画をみていた。
特に母が洋画のファンだったことが影響しているのかもしれない。映画とスポーツ中継(こちらは祖父と父の専売特許で、私は小学校と高校で野球部だった)の場合は、プロ野球中継と映画をハシゴして夜11時近くになっても、「早く寝ろ」とか「勉強しろ」とは言われなかった。
小学校の卒業の際、何人かの女の子たちがそれぞれの「思い出のアルバム帳」をクラスの男子に回してメッセージをもらっていた。
なんと私は「好きな女性はカトリーヌ・ドヌーヴ」とませたことを書いていた(赤面!)。
ミシェル・ルグランが美しいスコアを書いたミュージカル『シェルブールの雨傘』(1964年)のヒロイン役と人妻と娼婦を演じたルイス・ブニュエル監督の『昼顔』(1967年)の対比が、あまりにも強烈だったからである。チャーミングさと妖しい色気が同居していた名女優だった。(今でも第一線で活躍中!)
筑紫さんはイングリッド・バーグマンだったようだ。著書に「世の中にこんな美しい人が存在するのかと、ませたガキは仰ぎ見たものである」と記している。
バーグマンのブロマイドも買っていたらしい。
そして「最近は観る映画に迷った時は、女優で選んでいる」として、メラニー・グリフィスとキャメロン・ディアスの二人をあげている。私もともに好きな俳優なのだが、ここ10年のお気に入りの女優を二人あげるとすれば私の場合は、ケイト・ブランシェットとモニカ・ベルッチだろうか。彼女らの作品は大体観ている。
私が最初にはまったのは監督ではなく役者で、「The King of Cool」スティーヴ・マックィーンだった。
確か9歳の時に「ゴールデン洋画劇場」で前編・後編の2回に分けてテレビ初公開された『大脱走』(1963年製作・ジョン・スタージェス監督)をみたのが最初だ。
ナチスの追手から逃げてバイクでスイス国境を走りまくるアメリカ兵ヒルツの雄姿にガツンとやられた。
そして『ブリット』(1968年製作・ピーター・イェーツ監督)でサンフランシスコの坂道を猛スピードでカーチェイスする刑事役にしびれて中学時代にマックィーンの写真やサントラ盤を集めはじめた。
絵を描くのも好きだったので、中学の美術の授業で「LPジャケットか本の表紙のデザインを描く」という課題がでたときには、マックィーンが富豪の大泥棒を演じた『トーマス・クラウン・アフェアー』(1968年製作)のサントラ盤用にと、彼が足を組んで地球儀に腰かけている構図のジャケットをかいたりした。
(当時はVTRやDVDなんて存在しなかった。バイブルは『スクリーン』や『ロードショウ』という雑誌だったが、『ロードショウ』のほうは近く閉刊になると聞いた・・・なんだか寂しい)

対論・黒澤明
中学1年生の時、最初に小遣いをはたいて映画館で観た映画が、ジョン・ギラーミン監督の『タワーリング・インフェルノ』(1974年・日本公開は75年)だった。
格上のポール・ニューマンを完全に喰っていたし、『ジョーズ』や『スター・ウォーズ』で有名なジョン・ウィリアムズのテーマ曲も素晴らしかった。
マックィーン好きが昂じ、彼と共演したジャクリーン・ビセット、アリ・マッグロー、フェイ・ダナウェイを知り、彼女らのことも調べるようになった。
続いてはまったのがクリント・イーストウッド。
『シェーン』や『真昼の決闘』といった正統派の西部劇も好きだったが、葉巻にポンチョのニヒルな「マカロニ・ウェスタン」に熱をあげた。昭和30年代後半生まれの映画好き少年はみんなそうだったような気がする。エンニオ・モリコーネの音楽も影響大だった。
マックィーンは不幸にも早逝してしまった。
イーストウッドが違ったのは、ある時期から主演作の監督もやり始めたことだ。
ワープロなどなかった時代に手作りで彼の年表を作り始め、観た映画をチェックしたり、タイトルの横に「寸評」を記していった。

タワーリングインフェルノのポスター
1975年に監督・主演した『アイガー・サンクション』が転機だったように思う。
これはただ者ではないというある種、畏怖の念――少年の心にそう感じさせる凄さがあった。
テレビでみたときは、「濡れ場」がカットされていたように記憶しているが、その後ビデオを購入して完全版を見ると山岳サスペンスにエロティックな要素もちりばめられ、見返すたびに新鮮な驚きを感じる作品だ。
それから熱狂的な「イーストウッド信者」になり、大学時代から新作は必ず映画館で観、金を稼ぐようになってからは、彼のビデオ・DVDを買いあさり、それは今も続いている。
イーストウッドはハリウッドで最も客を呼べる男優の一人になり、かつ監督として大成功をおさめた唯一の人間である。(先日、藤原帰一さんとその話になって、お互いロバート・レッドフォードやショーン・ペンはどうかという議論になり、「やっぱり違うよね」という結論で一致した)
あのスピルバーグが「私たちの夢」と語っているほどの存在なのだ。
2005年の5月に放送された対論は、イーストウッドのほうが筑紫さんより5歳年上なのだが、同じようなオーラをもった「巨人対決」の趣きがあり、「23」の監督対論の中で私の中のベスト・ワンである。スクリーンでは寡黙なイメージがあるが、インタビューでは予想に反してとても饒舌だったのが印象に残っている。
一部を抜粋しよう。(CE:クリント・イーストウッド)
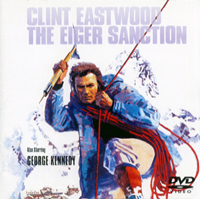
アイガー・サンクションのDVDジャケット

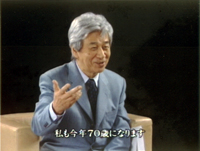
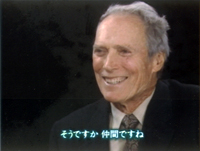

対論・クリント・イーストウッド
対談はこのあとイーストウッドが構想を温めていた「硫黄島二部作」に及ぶ。
三度目のオスカーは逃したが、悲惨な戦争を日米それぞれの視点から描いた力作だった。
筑紫さんは、こう尋ねている。
イーストウッドは俳優になる前に、溶鉱炉の火炊き、トラック運転手、海水浴場の救助員など様々な仕事を転々としている。監督兼役者として油がのりきっていた時期に休業して西海岸のカーメル市長を務めた経歴も持つ。
2005年は「ロスジェネ」という言葉に象徴される「フリーター」「引きこもり」といった社会問題がクローズ・アップされ、アメリカのブッシュ政権が「イラク戦争」にいれ込んでいた時期だ。巨匠が語る「人生論」と「戦争論/幸福論」は、ニュースバリューとしても十分な星がつく内容だ。
その言葉は、世界各地で戦火がやまない2008年の今でも、胸に響く。
学習院大教授の中条省平さんが『クリント・イーストウッド〜アメリカ映画史を再生する男』(ちくま文庫)の最終章に「二十一世紀のイーストウッドは十字架の彼方に」と題する文章を書いている。ここ数年の密度の濃い彼の活動を独自の視点で考察した読み応えのある評論だ。
イーストウッドは今も走り続けているが筑紫さんのテレビでの活動は、今のところ小休止している。しかし、私の心の中では二人が重なり合ってしょうがないのだ。かたや「映画界」、かたや「言論界」―――。
アクターであり、ディレクターであり、コンポーザーでもあるイーストウッド。
リポーターであり、コメンテーターであり、アンカーパーソンであり、プロデューサーでもある筑紫さん―――「二十一世紀の筑紫さんはどんな彼方に向かうのだろうか」
(追記:「筑紫哲也ニュース23」で取材・放送された監督対論は、非常に質の高い財産である。できればこの「WEB多事争論」で再録し、お見逃しになった方にご覧いただければと希望する)


「硫黄島二部作」











