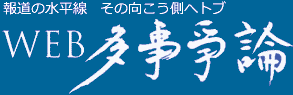- トップ >
- 続・カルチュアどんぶり >
- #8 健聴者とろう者の関係に優劣をみる不幸


金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」「沖縄ワジワジー通信」など多数。
#8 健聴者とろう者の関係に優劣をみる不幸
2014/01/23

(世田谷パブリック・シアターのポスターより)



(舞台写真;提供 世田谷パブリック・シアター)
これほどの緊張感を持続させられる舞台はそんなにあるわけではない。イギリスの劇作家ニーナ・レインの作品「Tribes」(翻訳・台本・木内宏昌 演出・熊林弘高)をみた。エリート臭の強い裕福な家庭(父、母、長男、次男、娘)。次男ビリーは生まれつき耳が聞こえない、ろう者だ。ビリーは健常な家族の一員として、それぞれが勝手に「クリエイティブな」主張をぶつけあう家族のなかで、ひとり物静かに沈黙している。そして家族たちはそのビリーを一見慈しんでいるようにもみえる。この家族の中では、ろう者ビリーを含めて微妙なバランスが成立しているのだ。父親によれば、ビリーは健常者である兄妹たちと分け隔てなく育てられた。それが「わが家の方針」なのだという。ある日、そのビリーが、自分に恋人ができたとして、シルビアという女性を家族の前に連れてくる。シルビアは両親ともにろう者で、いずれ自分も聴力を失う運命にあることを知っているのだが、「手話」という、ろう者のコミュニケーション言語を身につけている。このシルビアを演じているのが中嶋朋子だ。シルビアがこの家庭に闖入してくることによって、家族のなかに不可逆的変化が生じる。その中嶋の演技がすばらしい。特に手話が切ないほどに美しい。彼女の登場以降、舞台は、冒頭に記したように持続的な緊張に支配される。その緊張の源は一体どこから来るのだろうか。健聴者と同じ言葉を発しながら、手話を同時に操ることのできるシルビア。健聴者からろう者に徐々に移っていくシルビアの「私は普通じゃなくなっていく!」という叫びが、どちらの側にも痛切に突き刺さってくる。父親のクリストファーという男が、手話をめぐってシルビアと会話するシーンが実にこの演劇のテーマを暗示している。父親は手話を劣ったコミュニケーション言語としてみようとする。ろう者のコミュニケーション言語は健聴者のコミュニケーション言語よりも劣っていなければならない、欠損がなければならないという根深い差別観にとらわれているのだ。「ものごとに優劣は絶対にある」と言い放つ父親の存在は、健常者(健聴者を含む)を優位におく思想の象徴だ。ところがそれに対して手話で答えるさまをみると、観客である僕らも含めて、手話の世界の豊かさ、美しさを実感させられることになるのだ。休憩後の舞台で、手話を身につけたビリーが自我にめざめ、家族に対して攻撃的になっていくシーンもすばらしい。手話は美しいだけでなく、怒りを表現するときには音声以上に豊かになる。みている僕らが、問い詰められているような気持ちが沸いてくる。ああ、そうなのだ。あの緊張感の源のひとつは、この劇の「健聴者―ろう者」の関係のなかに、見ている僕ら自身が当事者として取りこまれてしまうことにあるのではないか。そして、おそらく、ろう者の人がこの劇をみた時にも同様の緊張感を感じるのではないか。「健聴者とろう者が一緒にみられる芝居が日本ではまだまだ少ない」というのは、この劇の手話指導を担当した手話コーディネーターの米内山陽子さんの指摘だ。米内山さんて、もしかして、あの日本のろう者演劇界のパイオニア・米内山明宏さんと関係があるのだろうか。もしかして娘さんではないか。劇が終わってからもしばらく緊張感が解けなかった。
こういう密度の濃い舞台が今年2度目のステージ観劇だった。今年の皮切りがインドでみたボリウッド・スタイルのミュージカルだったので、何だか頭がクラクラする思いだ。世界は広いし、多様だ。今年は時間をみつけてなるべくたくさん舞台をみるぞ。