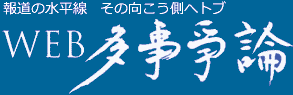- トップ >
- 続・カルチュアどんぶり >
- #11 「虚構」と「真実」の往復運動


金平茂紀(かねひら・しげのり)
1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」「沖縄ワジワジー通信」など多数。
#11 「虚構」と「真実」の往復運動
2014/03/12


(c) Final Cut for Real Aps, Piraya Film AS and Novaya Zemlya LTD, 2012
4月12日(土)、シアター・イメージフォーラム他にて全国順次公開
最近みた映画のなかで、これほど強烈な衝撃を自分のなかに残し続けている映画はない。そもそもこの『アクト・オブ・キリング』はドキュメンタリー「映画」なのか? もっと普遍的な地点にまで到達した、「映画」を越えてしまっている表現活動なのではないか。さまざまな解釈が成り立つ。「当事者による殺人行為の再現」という一種の演劇行為によって、真実に近づく「セラピー」のような要素もあり、あるいは誤解を恐れずに言えば、「エンターテインメント=娯楽」として途方もない行為を再現させているという要素さえもある。ジョシュア・オッペンハイマー(1974年アメリカ・テキサス州生まれ。以下JOと記す)というひとりの映画作家の強靭な執念を見せつけられた思いがする。ヴェルナー・ヘルツォークやエロール・モリスが激賞するのも無理はない。JOはインドネシアに長期間住んでインドネシア語を習得し、1965~66年のスカルノ→スハルトという政権移行期の混乱時に、国土の各地で起きた共産党員狩り(=100万とも200万ともいわれる大虐殺)を実際に行った実行者たちを取材した。そして、自らの殺人加担行為を自慢げに嬉々として語る彼らの「狂気」に接することになるのだが、驚くべきは、JOが、その実行者たちに映画作品化を持ちかけ同意を得て、彼ら自身が進んで虐殺行為を再現をしてみせるそのプロセス自体をまるごと映画にしてしまっていることだ。僕たちはよく、映画作品本編の付録/余興として製作された「メイキング・オブ・~」という代物をみることがあるが、この『アクト・オブ・キリング』はそうではなく、映画製作の過程そのものが本編なのである。虚構と真実の往復運動という現象がある。虐殺の実行行為が再現される=演じられることによって、虚構が真実を招致する。そのような現象が実際に起きてくることを、僕らはまざまざと見せつけられる。おそろしい映画だ。
この映画で僕の脳裏に焼き付いているいくつかのシーンがある。もちろんあのヘルツォーク的な幻想美に溢れた熱帯的イメージの映像。大きな滝を背景に巨大な金魚のオブジェの横で笑顔を浮かべながら踊り続ける実行者とインドネシア女性たちのシーンは映画全体の「狂気」を象徴しているようにさえ思える。そして、ある村での集団虐殺の再現にエキストラとして動員され老女やこどもたちが、実行者たちの迫真の演技によって、恐怖のあまり、失神し、泣き出すシーンも忘れられない。まさに「虚構」が「真実」になった場面だった。もうひとつだけ付け加えれば、僕はテレビ局で仕事をしているので、吐き気を催すようなパートなのだが、インドネシア公共放送のトークショーに虐殺の実行者たちがスタジオ出演して、かつての行為と映画のプロモーションのような話を嬉々として語っているシーン。グロテスクを通り越して、テレビというメディアが際限もなく堕ちていくサンプルを見せつけられた思いで、悲しくなった。
映画製作のプロセスのなかで、実行者たちが「変化」したようにもみえる。悔いあらためて改心したかのようにもみえる。そこに人間の希望をみようとする人々がいるかもしれない。本当にそうだろうか? むしろ「凡庸な悪」について記したハンナ・アーレントの洞察を僕らは想起すべきかもしれない。
この映画で提示された「狂気」はしかし、インドネシアという国の1965~66年に限られたあの時代の特殊な出来事なのではない。いま現在の僕らの生きている世界で、同様な「狂気」は生き延びている。偏狭な歴史認識や現状肯定、自己正当化に基づく「他者」「異物」「意見の異なるもの」「少数派」に対する排除の動きは、僕らのくににも、ほら、蔓延しているじゃないか。その意味でもこの『アクト・オブ・キリング』は、日本でみられるべき映画だと思う。